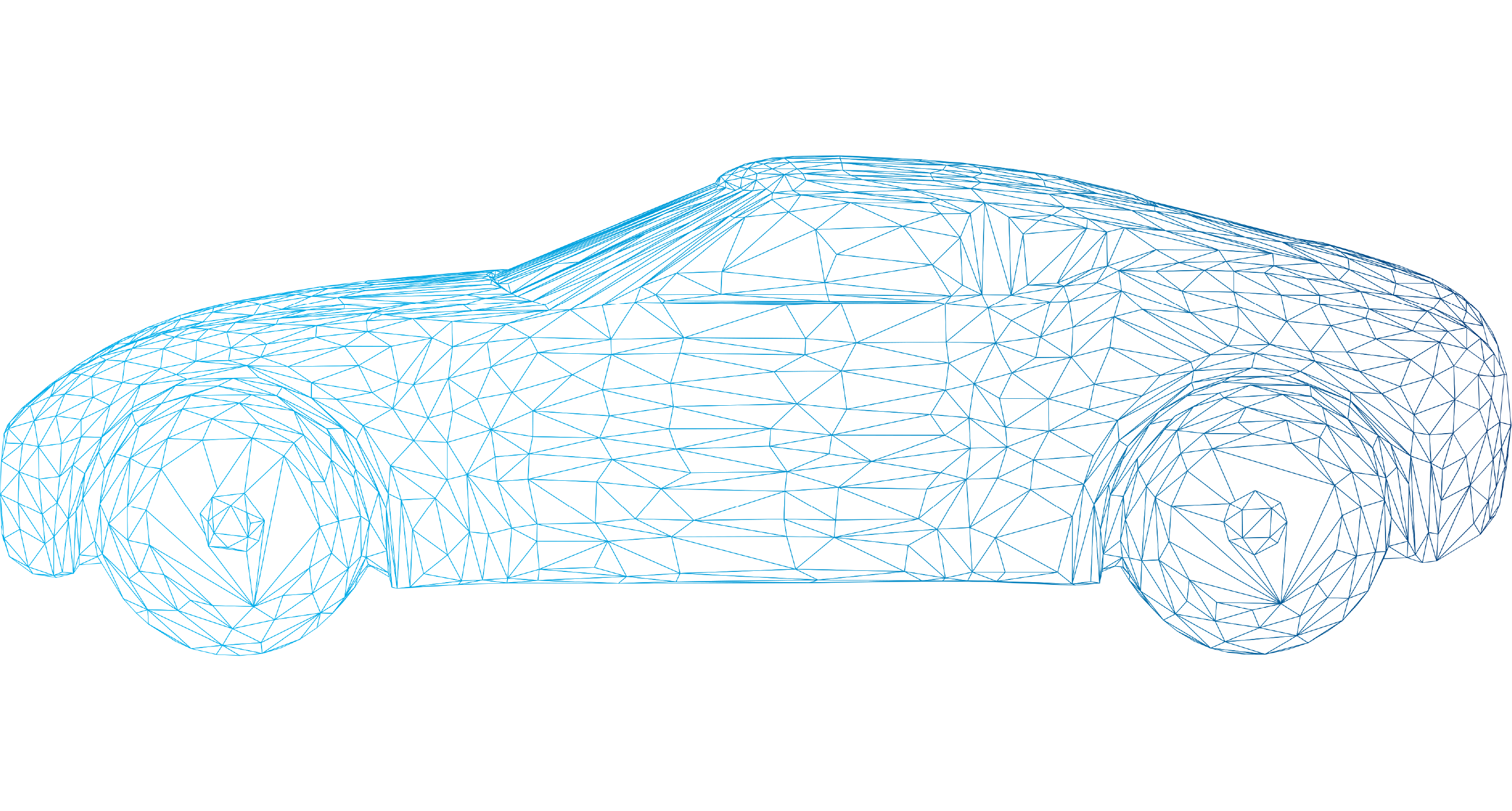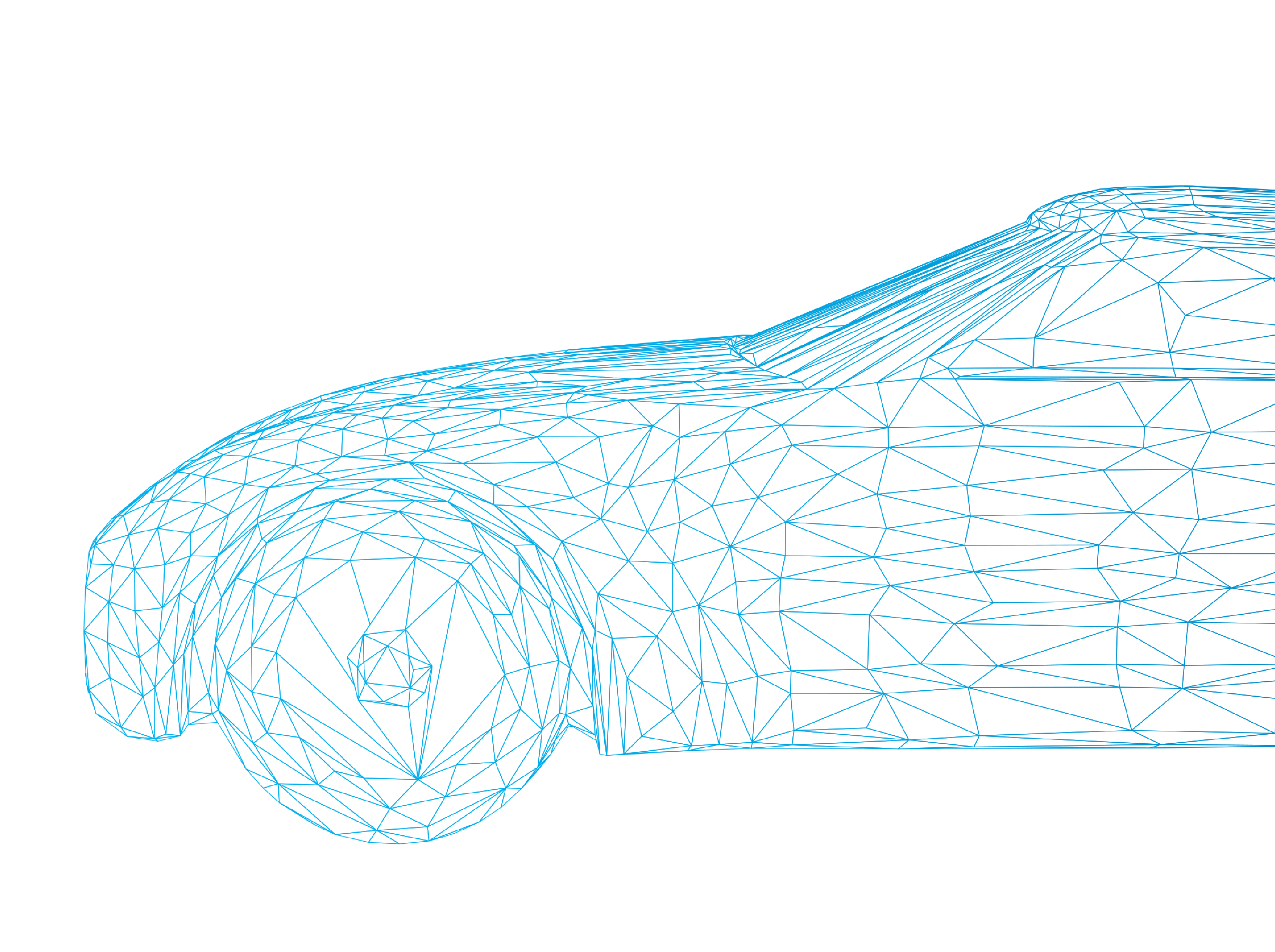日本への本格進出をスタートしたBYDが、「ATTO 3」に続いて導入するのがコンパクトEVの「ドルフィン」。エントリーモデルとなるハッチバックモデルには、電気自動車ならではの魅力と、BYDらしい独創性が見られるようだ。プロトタイプに国内試乗する機会を得た自動車ジャーナリスト・小川フミオが、感心させられたポイントを解説する。前回記事はこちら。価格に関する記事はこちら。 期待以上に広い室内空間 BYDが2023年9月20日に日本へ導入するドルフィン。車名はイルカだけれど、クロスオーバーのボディスタイルに、あまり関連はなさそう。 でも、インテリアでは“海”のモチーフが何ヵ所も、とBYD。内側のドアオープナーハンドルはイルカのヒレとか、ダッシュボード両端のエアアウトレットは“青海波”のような形状。 外観は開口部こそないけれど、ブラックアウトしたパネルがヘッドランプのあいだに設けられていることもあり、知らなければBEVとはわからないかも。 車体側面のリアフェンダーにかけての三角を橫にしたようなふくらみが独特で、これをおぼえていると、街中で見かけたときすぐ、ドルフィンだと気づくだろう。 Aピラーの付け根が前のほうに出ているのは、エンジンなどのマスをもたないと、ファイアウォールを前へ出せるため。その結果の、BEVならではのデザインだ。フォルクスワーゲンのID.シリーズとも通じる。 室内スペースは期待以上に広い。2,700mmのロングホイールベースで、しかも床面はフラット。後席にいても、かなりくつろげる。コンパクトな外寸ながら、4人で楽に使える利便性をもつ。 内装品質が高く、装備も充実 じつは、運転席で、もうひとつ印象深いことがある。作りの品質だ。合成樹脂の部品の品質感が高い。さらに、内装色に3つのバリエーションがあるのだが、小さなパーツまでカラーキー(色合わせ)されているのだ。 なかでも「コーラルピンク」というキラキラした薄いピンク色の車体色をもつ車両は、ピンク基調の内装色。シートは紫がかったピンクと、オフホワイトの組合せ。スイッチ類は少し黄味がかったシルバーだ。ブラックの内装だとここはブラック。 この徹底ぶりには感心。内装は、コストを反映する部分で、日本車だと特にこのところ、ちょっと手を抜いてるかなーと思うケースもあった。それがこのコンパクトなハッチバックで、というのに私は感心したのだ。 しかもというべきか、よくわからないけれど、シート材質は「ビーガンレザー」。ビーガン内装とは最近欧米で使われる用語で、意味するところは、本当の動物の皮革の不使用。 疑似レザーのほうがコストが高い場合もあって、メーカーによってはビーガン内装だと、プラスアルファのオプション料金を支払う必要がある。ちゃんとトレンドも押さえているのだ。 前席左右は電動調節式。シートヒーターもついている。エアコンのフィルターはPM2.5対応と、まるでたとえばボルボ車の解説を書いているような気になる装備の充実ぶりではないか。 ダッシュボード中央の12.8インチの液晶モニターは、ふだんは橫でも、スイッチで90度回転させればiPadのように縦で使える。ATTO 3でも導入されていた装備だ。小細工だということも出来るけれど、ユーザーはこういうところもなんとなく嬉しいだろう。 もし自分がドルフィンを買うときはどんな仕様にするだろう……と考えると、たしかにブラックとかブルーは無難だけれど、ピンクっていっそのこといいかもしれない、と思ったりする。 Vol. 3へ続く BYD DOLPHIN Long Range 全長:4,290mm 全幅:1,770mm 全高:1,550mm ホイールベース:2,700mm 車両重量:1,680kg 乗車定員:5名 交流電力量消費率:138Wh/km(WLTCモード) 一充電走行距離:476km(WLTCモード) 最高出力:150kW(204ps)/5,000-9,000rpm 最大トルク:310Nm(31.6kgm)/0-4,433rpm バッテリー総電力量:58.56kWh モーター数:前1基 トランスミッション:1速固定式 駆動方式:FWD フロントサスペンション:マクファーソン・ストラット リアサスペンション:マルチリンク フロントブレーキ:ベンチレーテッド・ディスク リアブレーキ:ソリッドディスク タイヤサイズ:前後 205/55R16 最小回転半径:5.2m 荷室容量:345-1,310L
メーカー別インタビュー記事