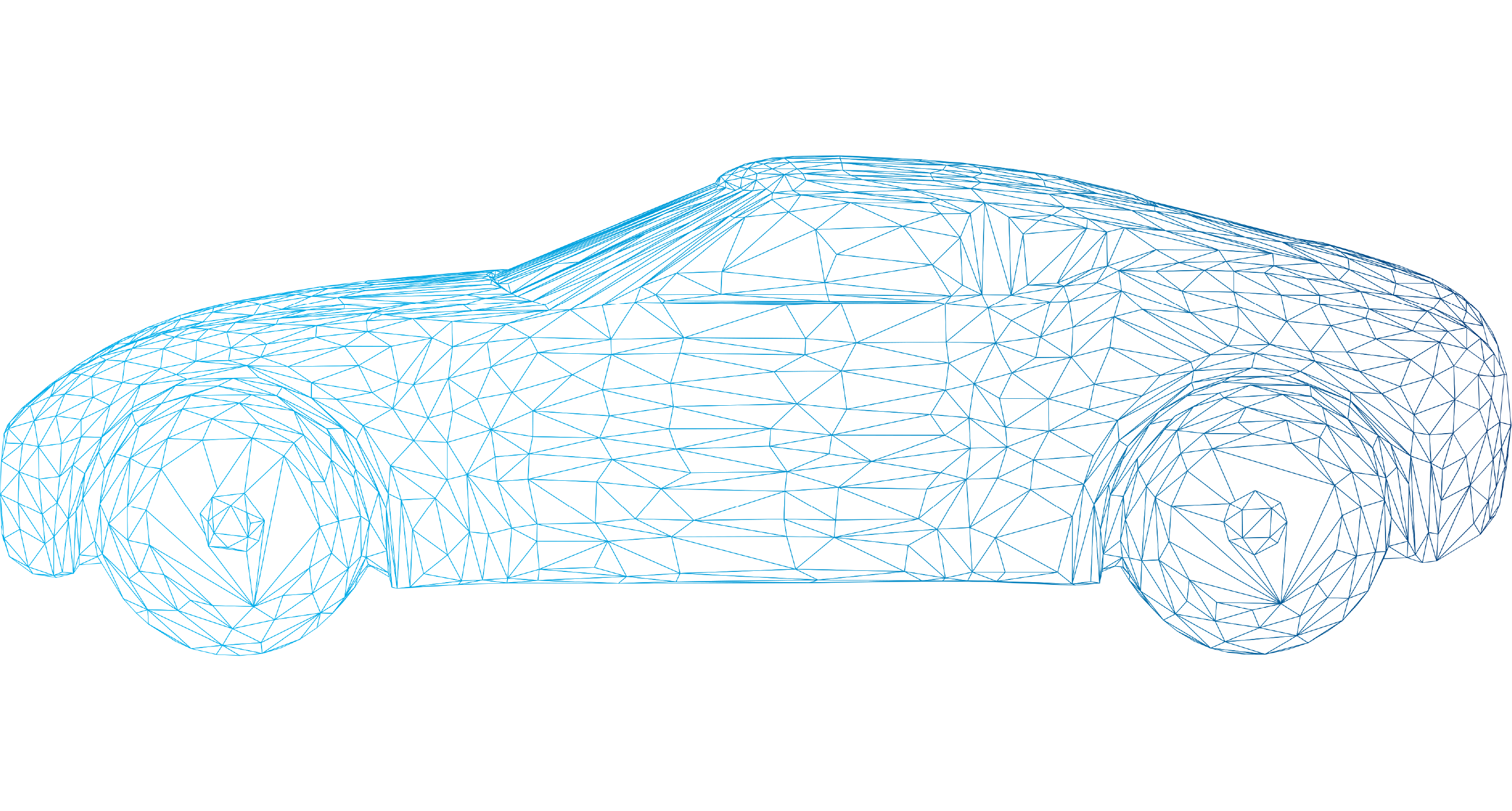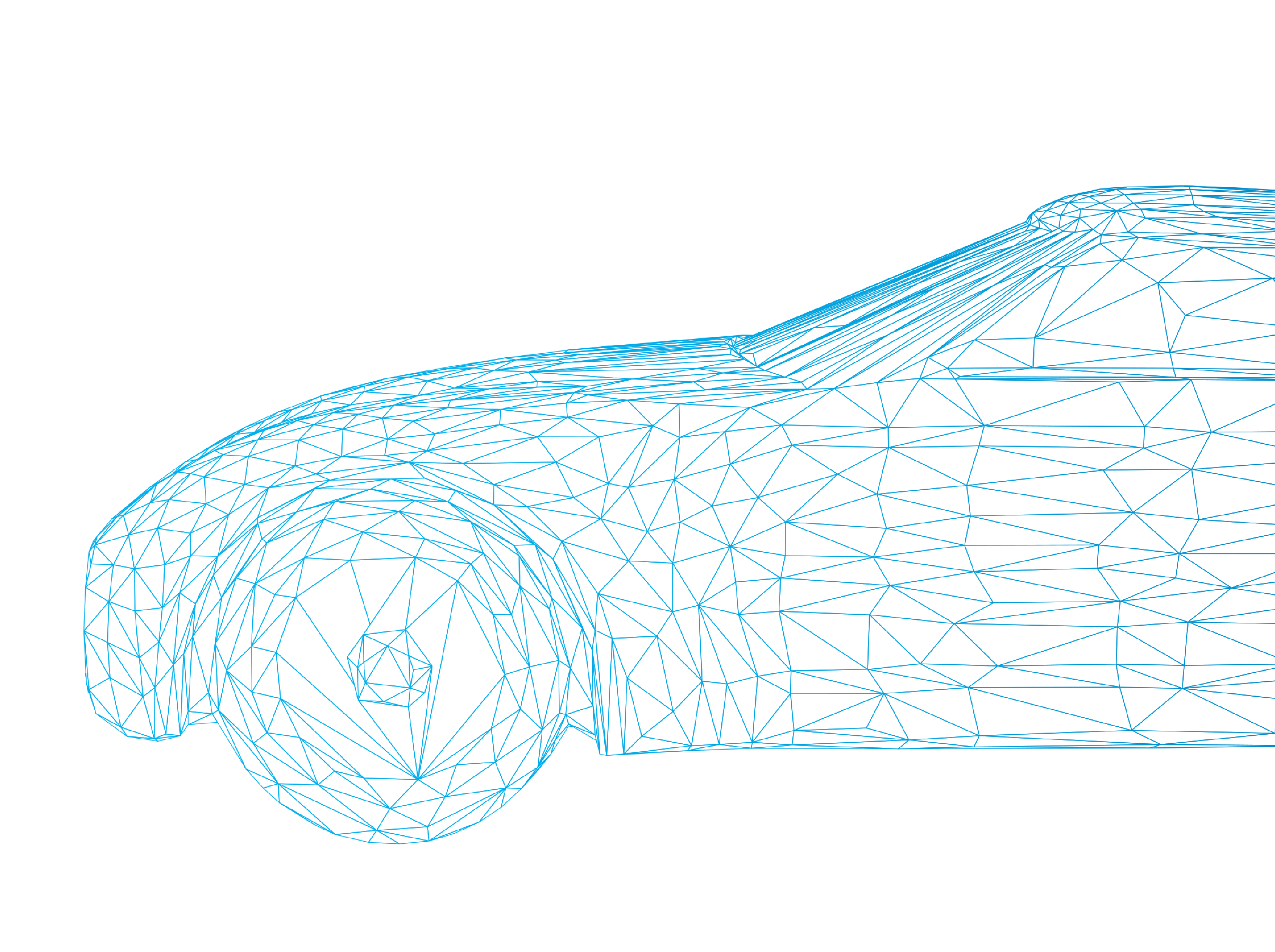EV専用プラットフォームを採用するアリアの走りをチェック。総じてレベルは高いが、改善すべきポイントも見えてきた。 低重心化のメリット EVの場合、背の高いSUVスタイルであっても、床下に重量のかさむバッテリーを搭載することで低重心化が図られ、走行時の安定性が確保されることが多い。アリアも例外ではなく、低重心化のメリットが見て取れる。 たとえば、SUVでは目立ちがちなロールやピッチングといった走行時の揺れは、このアリアではよく抑えられており、挙動は比較的落ち着いている。高速走行時の直進安定性も高く、目地段差を越えるときのショックも、さほど気にならない。ワインディングロードでは弱めのアンダーステアのおかげで、スポーティなドライビングが楽しめた。 ただし、荒れた路面を通過するような場面では、細かい上下動を伝えがちで、とくにリアからの軽いショックは気になるレベルだった。許容できる範囲ではあるが、今後のランニングチェンジで解消してほしいものだ。
メーカー別インタビュー記事