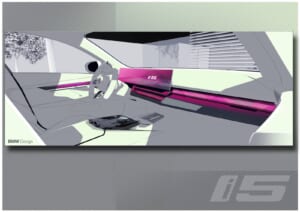もっとも静かで洗練されたレンジローバーを開発 2023年12月13日(現地時間)、ランドローバーは、レンジローバー初となる電気自動車モデル「レンジローバーエレクトリック」のティーザー画像および動画を公開。 同時に「レンジローバーエレクトリック」の予約を優先的に案内するプライオリティアクセスの登録サイトをオープンした。 「レンジローバー エレクトリック」は、極端な温度環境、あらゆる気候条件、どんな地形にも対応する走破能力、850mmの渡河水深を確保すべく、現在、プロトタイプを使ってテストを行なっているという。 エンジニアたちは、史上もっとも静かで洗練されたレンジローバーを開発するという目標を掲げ、独自のアクティブ・ロードノイズ・キャンセリング・システムとサウンドデザインに加え、モダンラグジュアリーを体現するEVならではの静穏で快適なキャビンを実現。 800Vのアーキテクチャーを採用し、公共充電ネットワークでの急速充電に対応する(欧州仕様)。 また、簡単な充電、エネルギーパートナーシップ、無線通信でソフトウェアのアップデートができるSoftware-Over-The-Air(SOTA)、航続距離を最大化する技術などシームレスなEVエクスペリエンスを提供。 レンジローバーの模範的なデザインを踏襲しながら、EVモデルならではの先進的なルックスを実現している。ぜひティーザー動画で確認してほしい!
#EV