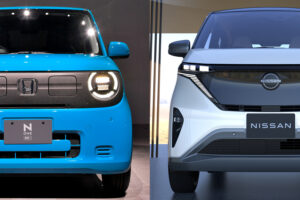日本に何が起こった? BEVが売れない……ハズが2025年10月は電気自動車が売れまくっていた
充電設定していない時間にブレーカーが落ちた! テスラモデルYの自宅充電は思ったより面倒な事態に!!
EVのメリットは、外出先でガソリンのように急速充電で電気を補充するだけでなく、自宅に置いているときにスマートフォンやPCのように充電しておき、いつでも満充電で走り出すことができるのがメリットだ。その自宅充電を行う際、充電器の設置工事が必要なのだが、その充電器を設置し運用した際、早くも障害が発生した。その原因を紹介する。