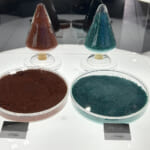水はどこから手に入れるのか?
ところで、水素への期待のひとつに、水の電気分解によって入手できるため、水素は無尽蔵のエネルギーといわれている。だが、その水はどこから手に入れるのかとの議論がなされずにいる。
地球は、水の星といわれるが、その98%は海水だ。淡水はわずか2%しかない。また、手近に使える淡水は、もっと少ないという見解もある。
そうしたなか、ユニセフ(unicef)によれば、安全に管理された水を利用できない人が世界に22億人いるとされる。これは、世界人口の約4分の1に相当する。人が生きるために飲む水さえ、不自由する人が大勢いるにもかかわらず、その淡水をFCVの水素を手に入れるために使うことが正義であるのか、考える必要があるだろう。
EVでは、車載バッテリーの重さが原因で大型トラックの利用に向かないとの見解から、FCトラックが出てきた。だが、米国テスラのセミは、EVのトレーラーヘッドだ。そして、満充電で約800km(500km仕様も選べる)走行できるという。
もちろん、日本で見かける多くが大型トラックであるのに対し、トレーラーヘッドでの輸送は、区別して検証する必要があるだろう。とはいえ、ディーゼルエンジンからの脱却という視点で考えるなら、よりよい選択肢へ向かっていく将来を見据える必要もある。
EVで課題となる充電も、すでに乗用車用のテスラのスーパーチャージャーによる急速充電性能の高さは知られるところだが、大型トレーラー用のセミへの充電には、メガチャージャーという充電が用いられ、30分で約70%の充電ができるという。
この充電性能は、荷物の積み降ろし作業や、運転者の休憩時間を活用することで、移動時間全体での損失を生じさせず、充電が完了する能力であると伝えられる。
とはいえ、それほどの超高性能な充電のための電力を確保する必要があり、その電力をどのような手段で得るかという視点が不可欠だ。
現在、AIを活用するデータセンターのために、原子力発電を再考する動きが米国などで起きはじめている。それらは、たとえ次世代型原子炉といっても、根本原理は軽水炉の延長線で、さらなる安全性と効率を高めているとはいえ、高レベル放射性廃棄物の課題を解決できるわけではない。
この点において、かねてより折に触れ紹介してきたトリウム溶融塩炉という新しい原子炉への挑戦は、単にメルトダウンをしないという高い安全性の確保に止まらず、高レベル放射性廃棄物をほとんど出さずに済む利点も考慮されるべきである。
そして中国では、実証炉が臨界に達し、発電をはじめている。
FCトラックも、EVトラックやトレーラーヘッドも、まだ検証しながら将来を見通す段階にある。そのなかで重要なのは、単に輸送手段としての性能だけでなく、世界80億人の人間が安心して安全に暮らせる日々を阻害しないことが前提だ。そこまでの広い視野がなければ、結局、いまの行動が無駄に帰すことになりかねない。