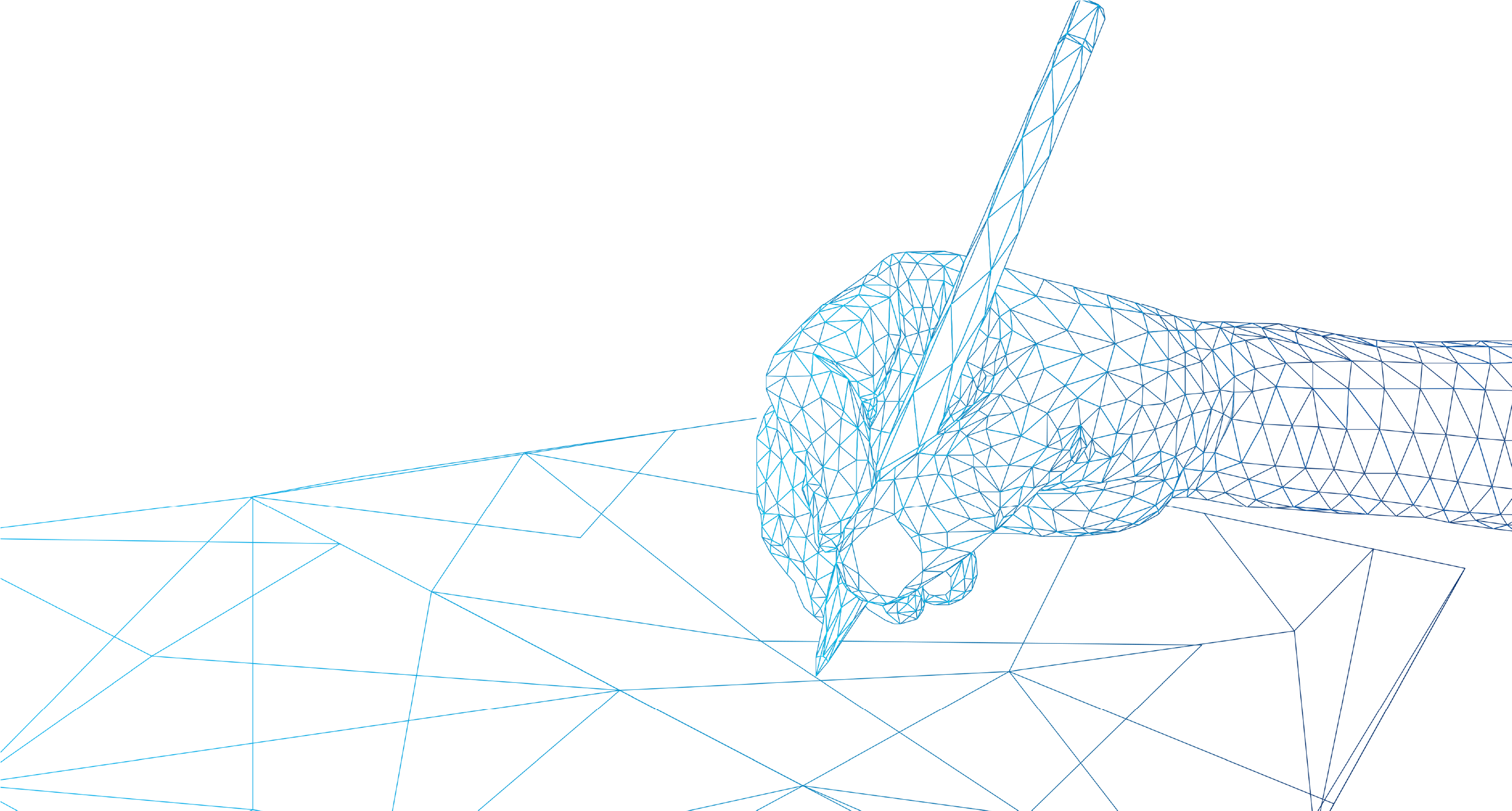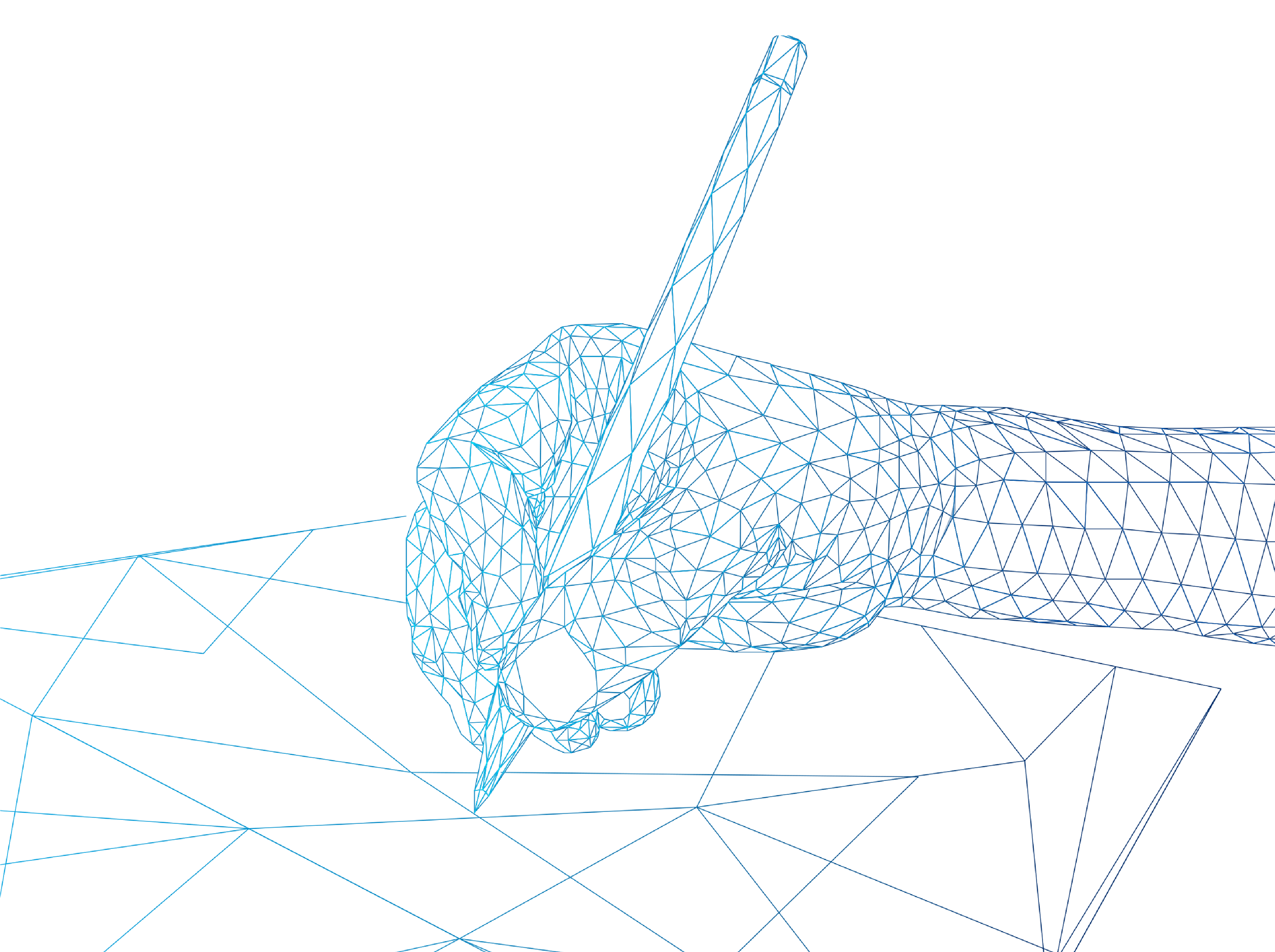BMWは2020年代後半に燃料電池車(FCEV)の発売を予定している。同社はなぜここまで水素にこだわるのか。そこには不確実な未来に向けて、BMWが考える戦略があった。 多様な電動化戦略 水素を近未来の燃料として有力視するのが、ドイツのBMWだ。さきごろ、「ジャパンモビリティショー2023」で、燃料電池車「iX5ハイドロジェン」をお披露目したBMWでは、これから電気と水素を両輪として進めていくと明言している。 私が以前、インタビューしたBMW取締役会のオリバー・ツィプセ会長は、「BEV(バッテリー駆動のEV)はあるところで頭打ちになる可能性がある」としていた。 南ヨーロッパは充電設備が少ないし、そもそもEVが普及していない地域で充電ステーションを建てても赤字になってしまう。なので、EVの普及がある台数に達すると、収益性が低くなる問題を引き起こす可能性が高い……それが指摘だった。 BMWが水素を使う燃料電池の開発を続けているのは、それだけでない。EUをはじめ、世界各地で水素燃料補給ステーションのネットワークが構築されつつあることもふまえ、多様な電動化戦略に合致しているというのだ。 そこまでは理解できる。しかし……と私は思う。乗用車、それもプレミアムクラスのスポーティなモデルに特化しているBMWが、そこまで水素に入れ込む意味はあるのだろうか。それこそ収益性の問題はクリアできるのだろうか。 「それはあります」。そう答えてくれたのは、水素技術におけるジェネラルプログラムマネージャーを務めるBMWのドクター・ユルゲン・グルドナーだ。下記に、ドクター・グルドナーとの一問一答の続きを記していこう。