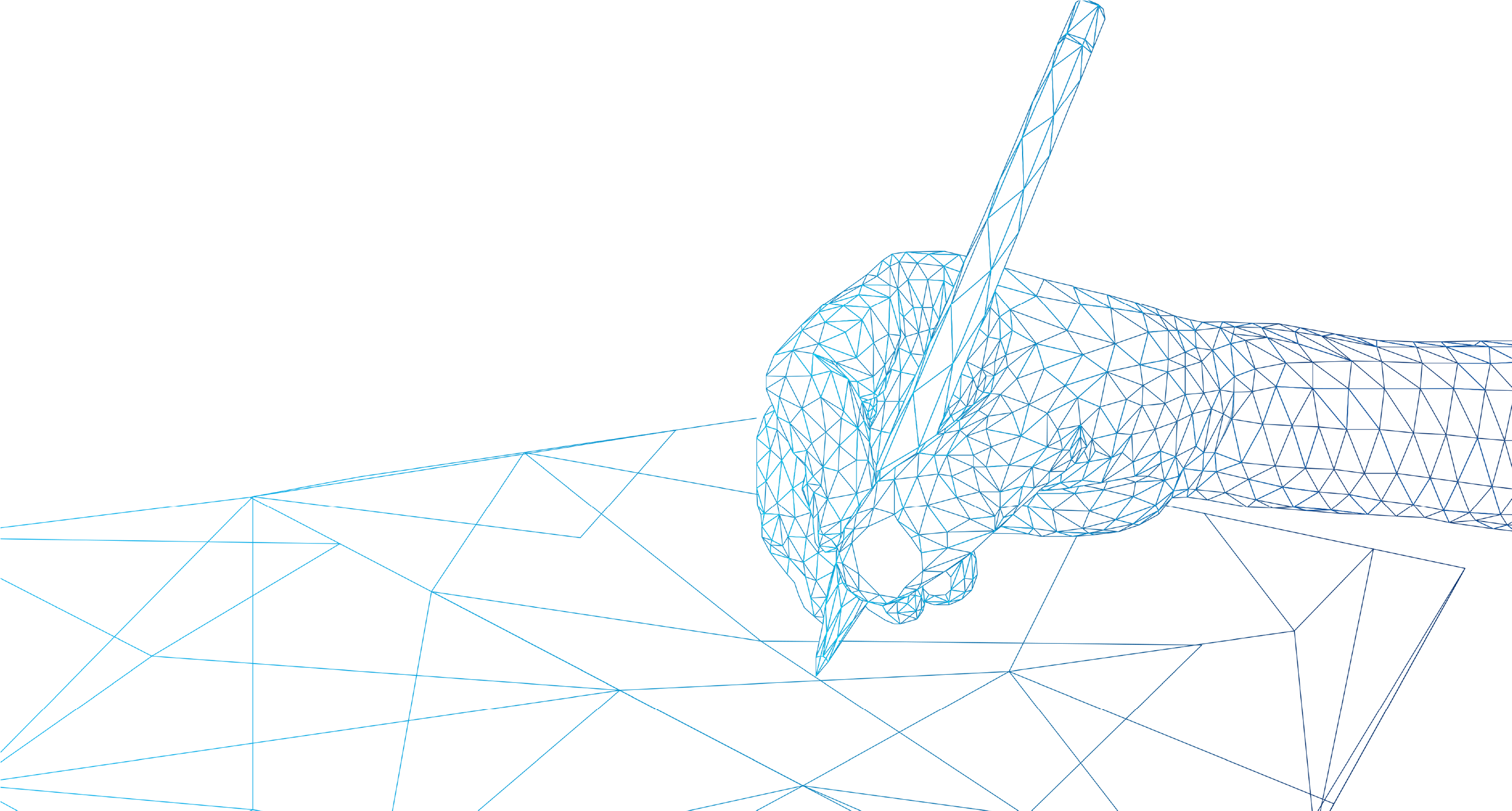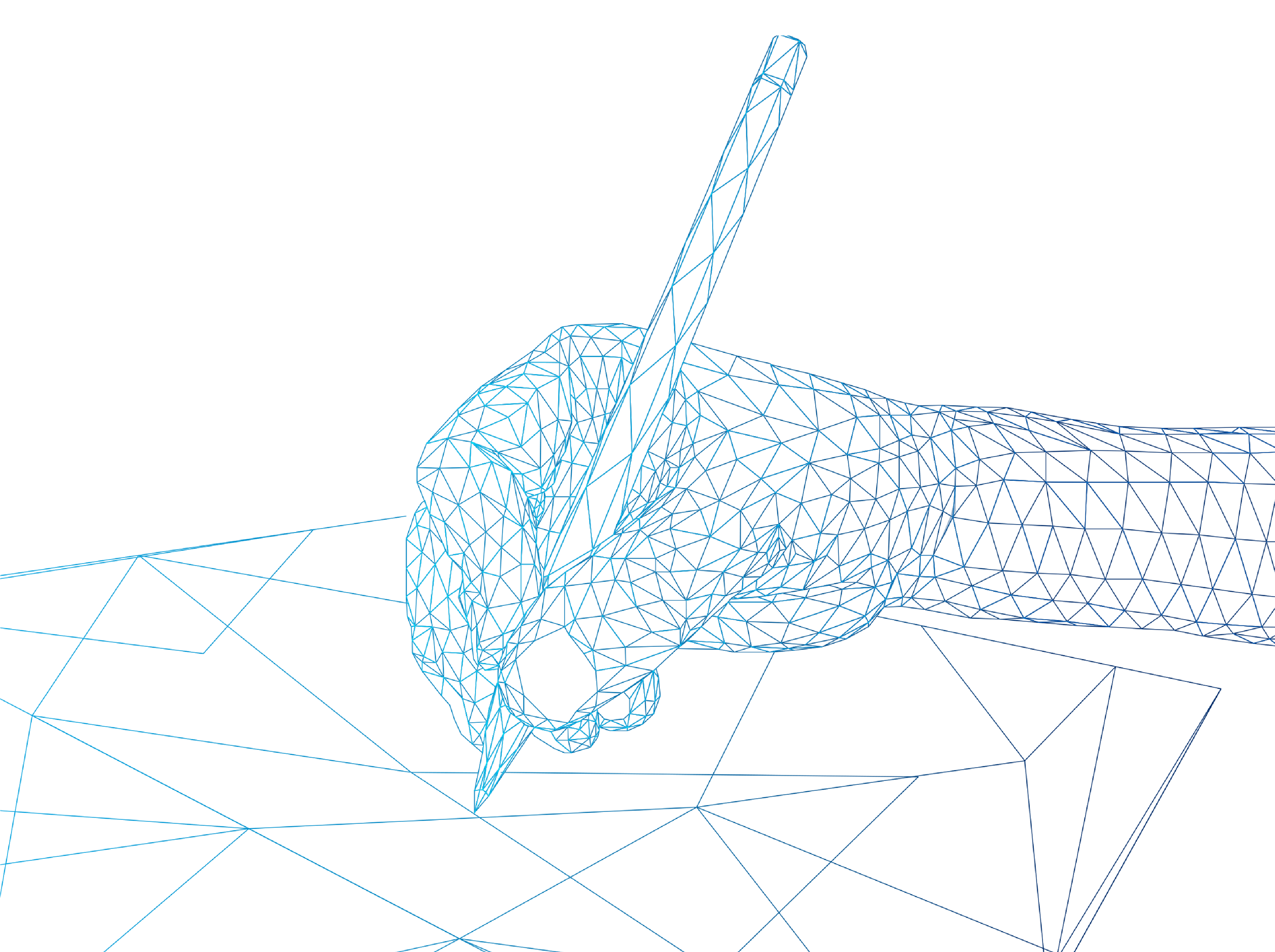ジャパンモビリティショーで話題となった「電座D9」。ショーを直前にした時期に、小川フミオは中国BYD本社で、このラグジュアリーミニバンを体感してきた。 電座Denzaの豪華ミニバン「D9」シリーズは、アルファード/ヴェルファイアとの近似性が指摘される。パッケージングはミニバンとして似通ってしまうのは仕方ないだろう。 ディメンション(ボディサイズ)は、ただし、D9のほうが大きく、ピュアEVが設定されている点では、さきを行く。 私が、2023年10月に運転したのは、プラグインハイブリッドの「D9 DM-i」と、ピュアEVの「D9 EV」。 外国人が公道で運転するのは原則的に許可されていないため、自分でハンドルを握ったのは、深圳にあるBYD本社の敷地内だった。 敷地内といっても、社員移動用に、スカイレールという高架鉄道が敷設されているほど広大。本社とさまざまな関連施設と、それに工場があるのだから、ひとつの小さな街ぐらいにはなる。 BYD本社の敷地内で試すハンドリングと後席の居心地 まずドライブしたのは、D9 DM-iだ。1.5リッターのエンジンに、外部充電式のハイブリッドシステムが組み合わせてある。 最大トルクが681Nm(AWD)というだけあって、踏み始めからたいへんスムーズな加速で、加速していってもボディはいやな振動もなく、ハンドリングはすなおで、遊びも少なく、扱いやすいという印象が強かった。 プレミアムクラスのミニバンは、後席の快適性とともに、ドライバーには、それなりのファン・トゥ・ドライブ性が必要となる。そこもちゃんとクリアしていると感じられた。 満充電なら190kmは電気走行なので、エンジンが回ったときの印象は(残念ながら)わからなかった。エンジンは、ゴルフとか家族旅行とかで遠出する機会の多いひとなら、あったほうがよさそうだ。そういうひとには、このモデルがいいのだろう。 いっぽう、D9 EVは、こちらもよく出来ている。上記のとおり、DM-iでエンジンが回ったまま走行すると、どんなフィールなのかわからなかったので、ちゃんと比較できないのだが(すみません)。 速度が上がっても、静粛。ウインドウまわりからの音も、路面からの音もほとんど気にならない。バッテリーによって重心高が下がっているのも、ハンドリングのよさに寄与しているのだろう。運転が好きなひとも好感もてそうだと思った。 EVモデルでは、後席で移動する機会もあった。シートクッションはふかふかっとしているが、いわゆる腰があって、2~3時間ていどの乗車では、からだに負担がかかることもなく、快適。 バックレストを、いわゆるプレミアムエノコミークラスのシート程度にリクラインさせて乗れるし、レッグレストもでてくる。が、私はじつはあれが落ち着かない。ちょこんとまっすぐな姿勢で乗っているのが好きである。 でも、休んで移動したいというひとなら、これはアリだと思う。 「電座」の日本導入は未定 ジャパンモビリティショーでは、トヨタ車体が、レクサスLMやクラウンSUVなみに2列めシートがほぼフルフラットになる「ヴェルファイア・スペーシャスラウンジ(コンセプト)」を出展した。 すぐにでも注文を受けられる状態と聞いたので、この点は、トヨタ系が先に行っていると言えるかもしれない。 ただし、「電座ブランドの日本販売はいまのところ未定」(BYDオートジャパンのマーケティング責任者)とのことで、ピュアEVのミニバンという、少なくとも東京など都市内では活躍してくれそうなD9 EVは、いまはおあずけ。よく出来てるクルマだったので、ちょっと残念だ。 <了>