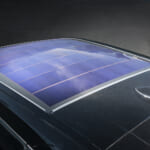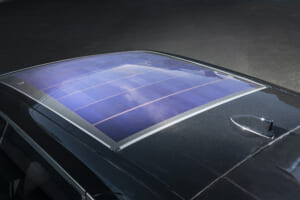至るところにNISMO専用チューン 日産自動車は2024年3月8日、1月に開催された東京オートサロン2024で公開した「日産アリア NISMO」を発表するとともに、「日産アリア」のB6 e-4ORCE、B9 2WD、B9 e-4ORCE、B9 e-4ORCE プレミアを3月下旬より発売すると発表した。なお、「日産アリア NISMO」の発売は6月を予定している。 アリアNISMOはベースモデルのアリアe-4ORCEに、NISMO専用の加速チューニングを施し圧倒的な動力性能をさらに引き上げた、EV NISMOのフラグシップモデルだ。NISMOの性能コンセプトである「より速く、気持ち良く、安心して走れる車」に基づき、高い安定性と軽快さを実現し、走りの上質感を磨き上げたという。 幅広い温度域において安定した性能を維持するブレーキパッドや、素材から内部構造に至るまでこだわり抜いたアリアNISMO専用開発のタイヤ、軽量化とリム幅のワイド化を両立しながら空力性能にも貢献したデザインのホイールを採用している。あわせてシャシーにおいては、前後のサスペンションやスタビライザーに専用のチューニングを施し、スポーティでありながらも、EVらしい滑らかで上質な走りを実現している。 電動駆動4輪制御技術をNISMO専用にチューニングした「NISMO tuned e-4ORCE」は、さまざまなシチュエーションにおいて高いトラクション性能を誇り、電動車ならではの爽快な旋回加速を実現している。また、ワインディングなどにおいても、スポーツカーのような高いライントレース性や思い通りのコーナリングを可能とした。 エクステリアはベースモデルのアリアが持つ上質さと、空力性能を向上させるNISMOらしいダイナミックなパフォーマンスを体現したデザインが与えられている。NISMO専用のバンパー、リヤスポイラー、ドア・サイドモールを採用し、洗練されたスタイリングでありながらも、空気抵抗の低減とダウンフォースの向上を高い次元で両立している。 インテリアは、黒を基調としたなかにスパイスの効いたレッドアクセントを配し、上質でスポーティな空間を作り上げた。スポーツ走行に合わせてホールド性とフィット感を高めた専用シートを採用し、車両との一体感を感じられる仕様となっている。また、オプション設定のNISMO専用BOSE プレミアムサウンドシステムを装着した場合、NISMOモードをオンにするとフォーミュラEマシンのようなEVサウンドの演出により、高揚感のある走りが楽しめるという。 ボディカラーは、NISMOステルスグレーに黒ルーフの2トーンをはじめ、全6色がラインアップされた。 ベースモデルのアリアはラインアップの見直しが図られた。力強い加速、滑らかな走り、EVならではの静粛性と、心地よい室内空間を兼ね備えたクロスオーバーEVというアリアの特徴はそのままに、顧客ニーズに合わせて2種類のバッテリーサイズと2種類の駆動方式がラインアップされた。注文受付を一時停止していたB6 2WDグレードの注文受付が再開されることに加え、B6 e-4ORCE、B9 2WD、B9 e-4ORCE、B9 e-4ORCE プレミアという4つのグレードが追加発売される。2021年の発売当初にもB9グレードは用意されていたが、車両供給体制の問題から納車が叶わず、今回仕切り直して発売される格好だ。 エントリーグレードのB6 2WDは通勤や買い物などの日常使いに加え、週末のドライブにも十分な航続距離を持つグレードではあるが、よりロングドライブを楽しみたいという場合には、バッテリー容量が66kWhから91kWhにアップしたB9 2WDがおすすめだ。さらにe-4ORCEを搭載したB6 e-4ORCE、B9 e-4ORCEも設定されている。 前後2基の高出力モーターと左右のブレーキを統合制御することで、4輪の駆動力を最適化し、あらゆるシーンや路面状況においてワクワクした走り、そして乗る人すべてに快適な乗り心地を提供するのがe-4ORCEだ。最上級グレードとなるB9 e-4ORCE プレミアには、ロングドライブをサポートする先進運転支援システム「プロパイロット2.0」や、20インチ専用アルミホイール、本革シートをはじめとする特別な装備が標準設定されている。 なかなか安定して車両を供給することが難しかったアリアではあるが、NISMOモデルの追加と受注再開で、再び国産EVファンから注目を浴びることは間違いないだろう。
#SUV