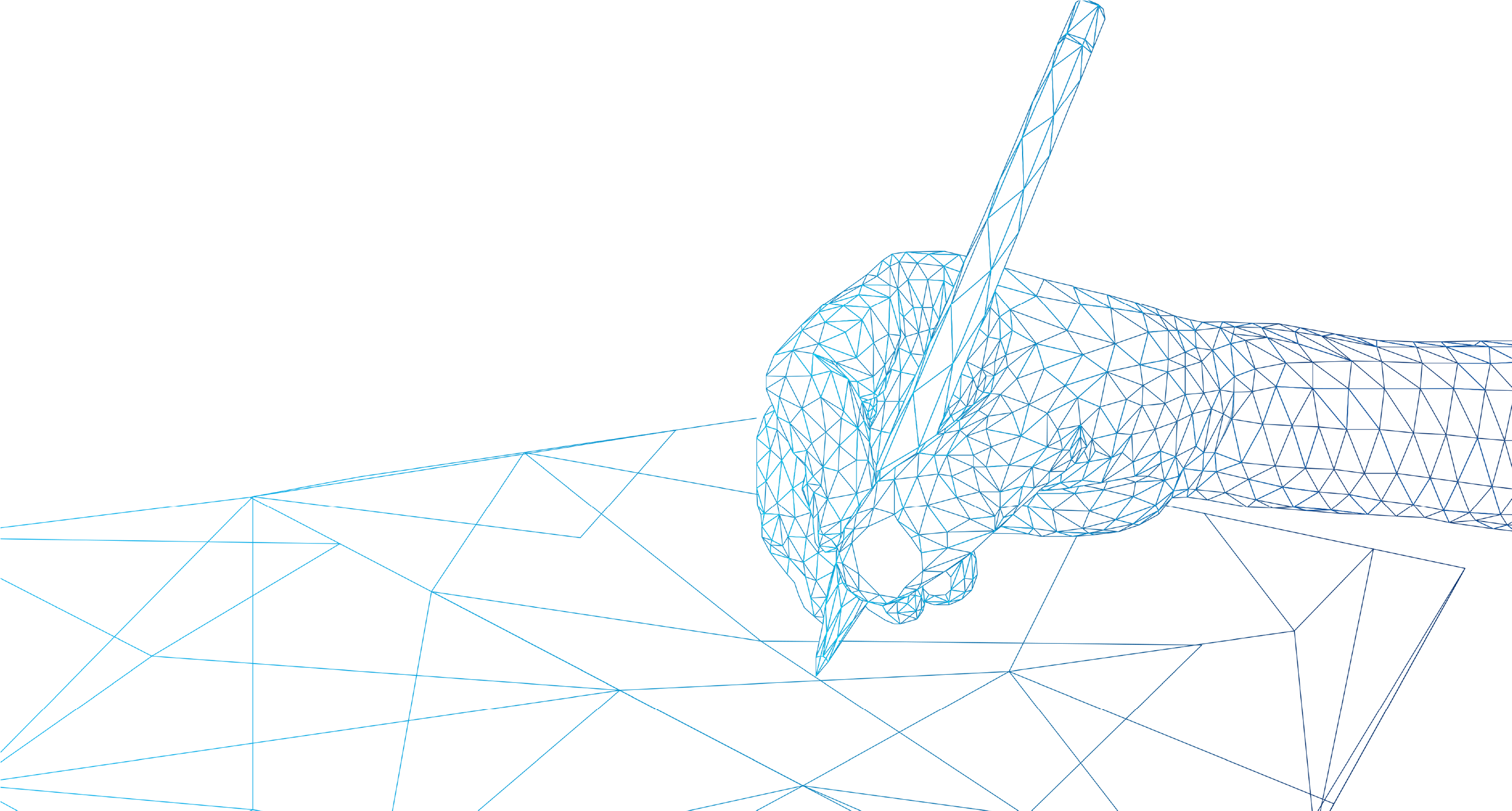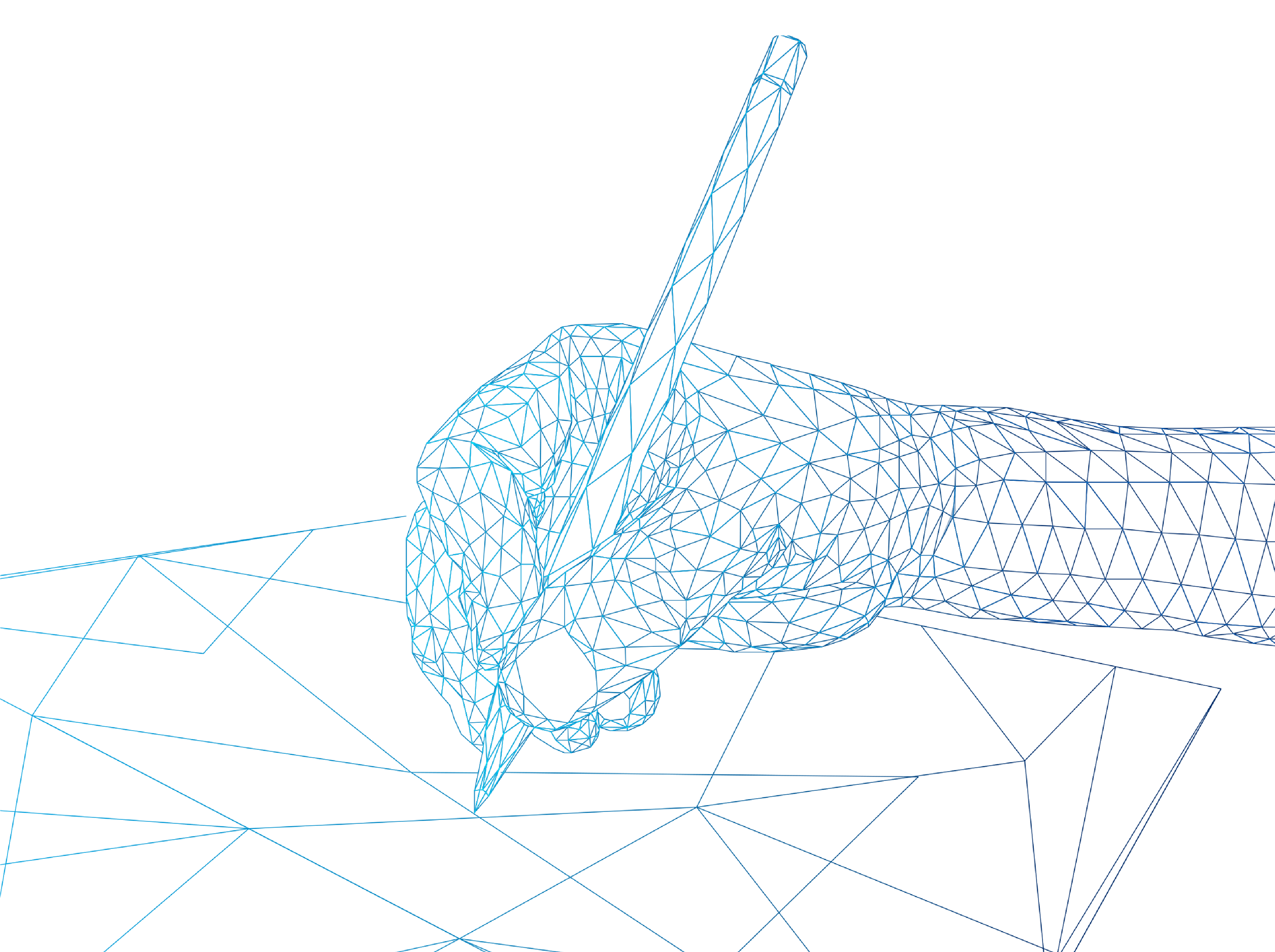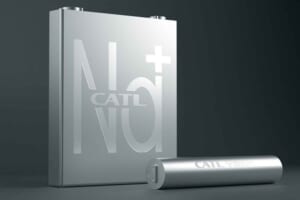人気アクセサリー3点とETC車載器まで付いて価格据え置き フィアットのEV「600e」に、発売以来初の特別仕様車「600e La Prima White Package」の設定だ。3月29日(土)に発売開始、全国のフィアット正規ディーラーで取り扱う。 「600e La Prima White Package」は、通常モデル「600e La Prima」の装備をベースとしながら、ホワイトで統一された人気アクセサリー3点と、高速道路での移動に不可欠なETC車載器が特別装備された特別仕様車だ。 特別装備 ・自動防眩ルームミラー(ホワイト) ・ホワイト仕上げミラーキャップ ・FIATホワイトエンブレム(フロント/リヤ) ・ETC1.0 車載機 これら総額約11万円分のアクセサリーと機器を搭載しながらも、価格は通常モデルと同額に据え置かれているので、お買い得な特別仕様車といえよう。 さらに「600e La Prima White Package」を購入すると、成約特典として車内でも使える高性能空気清浄機「Airdog mini」がプレゼントされる。置き場所を選ばないペットボトルサイズの空気清浄機は、車内のニオイや花粉、ウイルス対策に効果を発揮してくれそうだ。 このほか、「600e La Prima White Package」の発売を記念して、3月29日(土)~ 30日(日)にデビューフェアが実施される。特設サイトより申し込みのうえ、フェア期間中に全国のフィアット正規ディーラーを訪れると、「フィアット オリジナル ステンレスボトル」がもらえるというので、気になっていた人はぜひこのタイミングで足を運んでみてほしい。 ホワイトのアクセサリーをさりげなく随所にあしらった統一感のある外装は、ちょっとお洒落でありながらカジュアルにEVを乗りこなしたいオーナーにおすすめの1台といえそうだ。フィアット600eの特別仕様車「600e La Prima White Package」は、メーカー希望小売価格585万円(税込み)となっている。