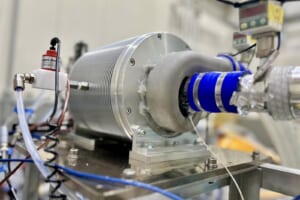モータースポーツ業界の起爆剤として期待 違和感を覚えたトムスのEVカート開発 トヨタ車のカスタマイズ・チューニングパーツの開発販売と、国内屈指の強豪レーシングチームを運営するトムスが、ここまでEVカートに熱心だったとは恐れ入った。 遡ること2年前。突如トムスがEVカートの開発ならびに全日本カート選手権にEVクラスを新設すると発表した。それまでレーシングフィールドで培った技術を、市販乗用車向けパーツに還元する形でその開発・技術力を証明してきていたものの、それがレーシングカートとなると少々畑違いな気がした。 それが、2024年5月30日にシティーサーキット東京ベイで行われた全日本カート選手権EV部門の参戦ドライバー最終選考会議、およびチーム体制発表会を取材して、考えが180度変わった。この取り組みに対し、ひとりのモータースポーツファンとして大いに応援したい気持ちになった理由を報告したい。 トムスのEVカートは「TOM’S EVK22」と呼ばれ、出力24kW、最大トルク100Nm、最高速度125km、0-100km/h加速は4.0秒という性能を持つ。これがどのぐらいの性能なのかというと、新東京サーキットでのラップタイムは全日本カート選手権の最高峰クラス「OKクラス」のわずか2秒落ち、入門カテゴリーの「KTクラス」に比べると5秒ほど速く、レーシングカートとして必要十分な性能を持つ。 今回の発表会は、前半が大会の概要説明、後半が2024年度の全日本カート選手権EV部門の各チーム参戦体制発表、ならびに参戦ドライバーのドラフト会議といった構成で行われた。 本稿では、前半の大会概要説明の部分について触れていきたいが、重要なのは開催に至る背景と取り組み方で、それこそが180度考えが変わった点だ。なので、そこにフォーカスして以下お伝えしたいと思う。 カートを取り巻く現状 大会概要説明はトムス代表取締役社長の谷本勲氏から行われ、モータースポーツにおいてのカートの立ち位置から話が始まった。サーキット四輪レースを頂点とした場合、本来カートは身近な存在であり、だれもが気軽に体験できるモータースポーツの入口ではないかと谷本氏は説く。 事実、現在国内外で活躍するトップドライバーの多くは幼いころからレーシングカートで経験を積み、四輪レースへと昇格している。また、成人であっても趣味としてカートを楽しむ方は多く、スポーツとして見た場合の対象年齢は幅広い。野球で例えるなら、軒先でのキャッチボールに始まり、地域の少年野球団から高校野球を経てプロ野球に入団するステップアップの面もあれば、社会人になってから趣味で草野球に参加するのも、野球というスポーツを楽しむひとつの在り方で、カートもそうなっていなければならないということだ。それだけにカートはモータースポーツ業界全体にとって入口であり重要だ。 しかし、カート競技に出場するためのライセンス発給数は、1995年の9703人をピークに、2023年には4863人まで減少しているという。 この統計変化について谷本氏は、1980年代末から1990年代前半までの第1次F1ブームを例に挙げた。選手に憧れてカートを始めたり、F1ブームにあやかったテレビ番組やコンテンツに影響されて始めたりといった背景が大きく影響したのではないかと分析する。 かくいう私も、小学生の頃、お昼の人気番組にアイルトン・セナや片山右京がゲスト出演したのを見たし、他番組では星野一義、鈴木亜久里、近藤真彦といった国内のトップドライバーが芸能人とカート勝負をして番組を盛り上げ、カートの魅力に引き込まれた記憶がある。それが直接的なきっかけかは記憶が定かではないものの、同級生を誘っていまは無き多摩テックや自転車で行ける範囲にあったレンタルカート場に、なけなしの小遣いで通ったりもした。 しかし、いまはどうだろう。地上波テレビ番組はおろか、Youtubeをはじめとしたインフルエンサーマーケティング、動画コンテンツにおいては、有名人の自動車カスタムや経営者層が乗る高級スポーツカーの自慢大会こそあれども、自動車レースの原体験的なカートを取り上げたコンテンツは非常に少ない印象だ。 加えて全国に約80箇所あるカートコースは売上がピーク時の5分の1にまで減少し、ライセンス発給数以上にカートを体験する人数が減少し、市場がシュリンクしているではないかと谷本氏は現状を憂いている。それは競技会の開催数も同様で減少の一途だ。 この現状を打破し、モータースポーツ業界全体の活性化につなげたいということで、奮い立ったのがトムスでありEVカートなのだ。