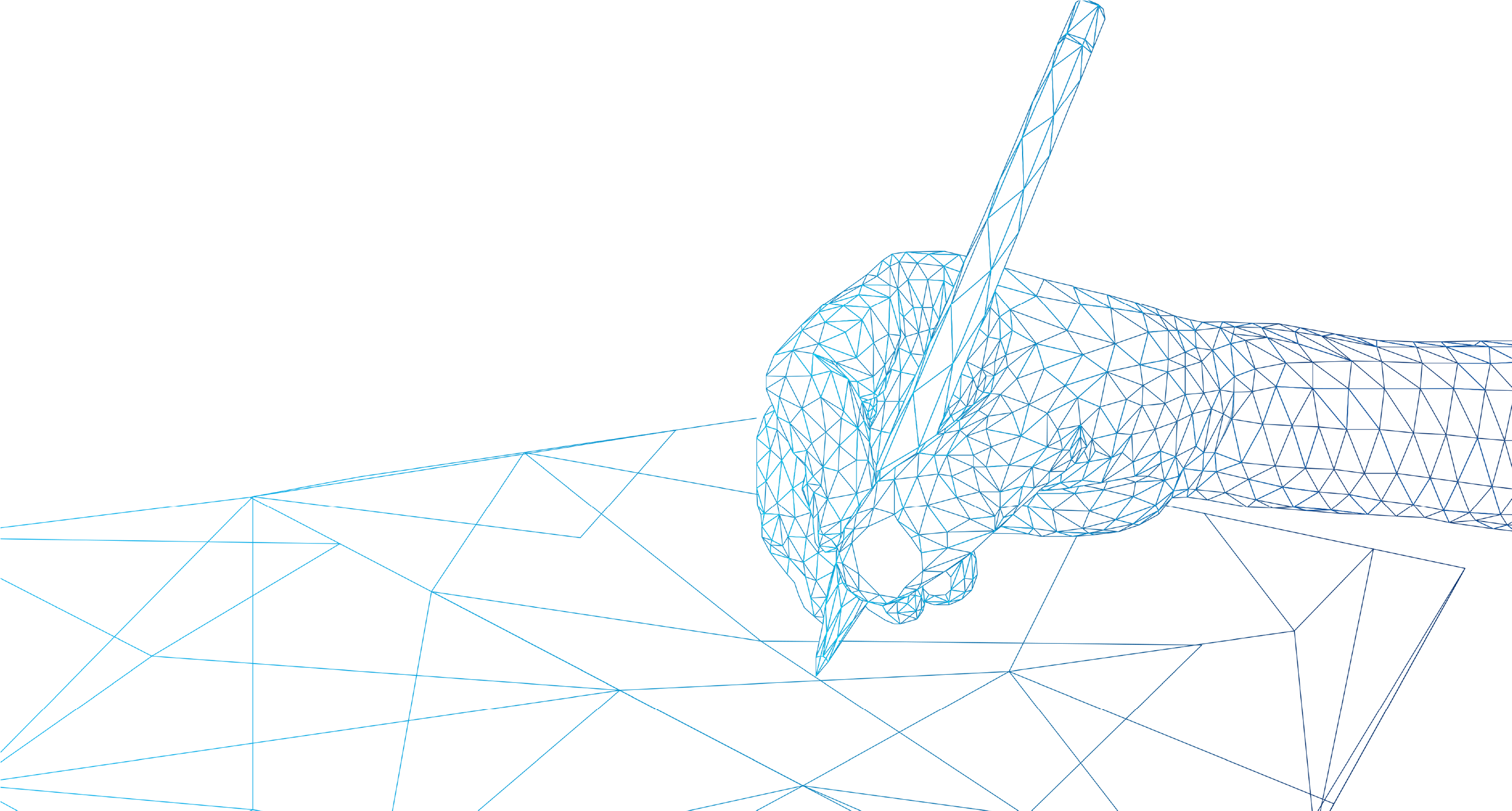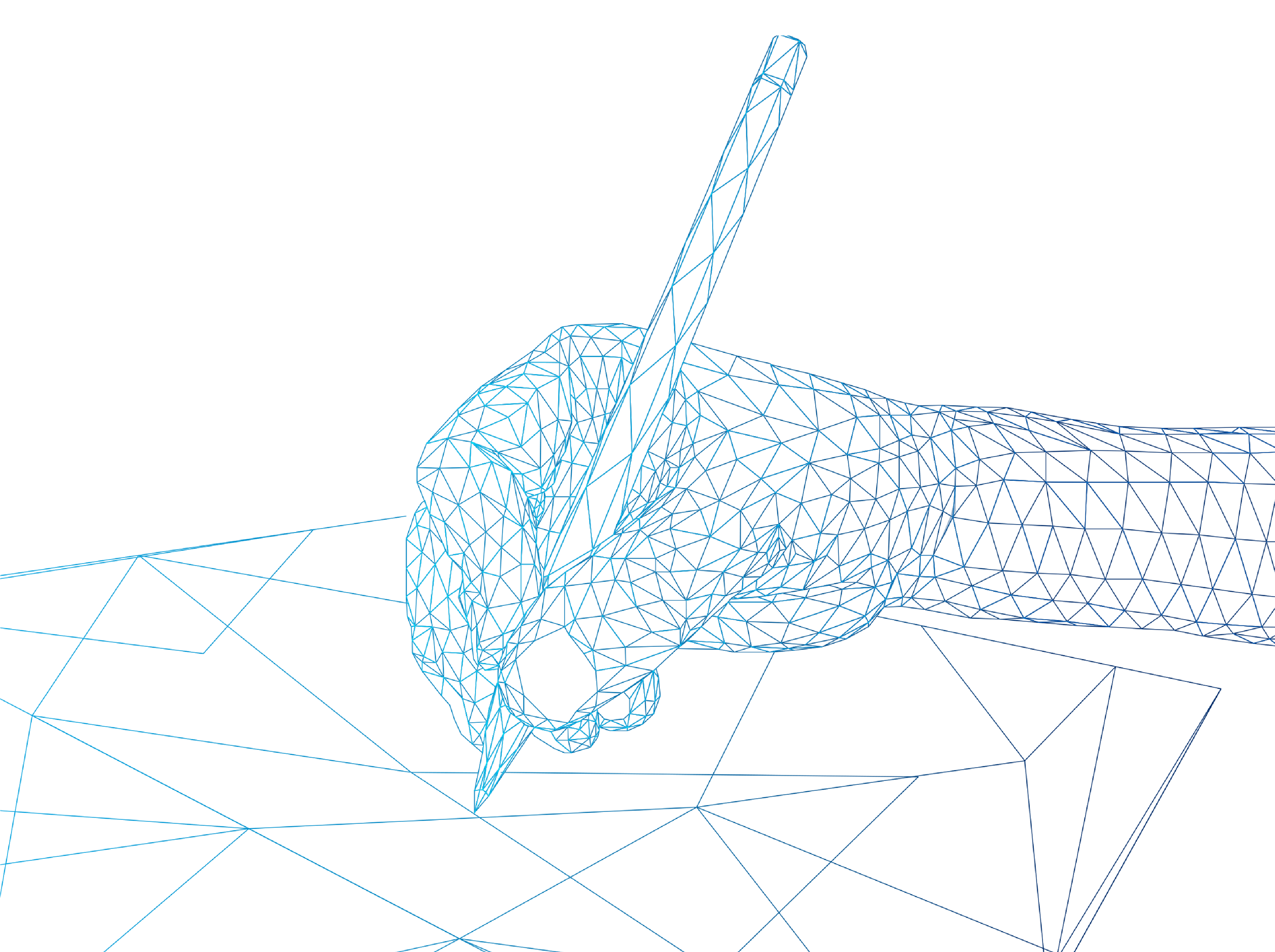「消防展」レポートの後編は消防車以外の支援機器類を紹介 活用が進んでいるEVの三輪バイク 日本最大級の消防・防災に関する展示会「東京国際消防防災展2023」(主催:東京消防庁/東京ビッグサイト/東京国際消防防災展2023実行委員会)が、6月15日〜18日に東京ビッグサイト<東京都江東区>にて開催された。 前回のレポート[詳細はこちら<click>]では、展示会の花形と言える消防車のEVを紹介した。しかし火災は消防車だけで消火することはできず、様々な支援機器を適宜使用することで完遂できるものといえる。何より消防活動は人命活動が第一。火災だけではなく、昨今激甚化している水害への対応も求められるため機器類も進化している。そこにはもちろん電動技術が取り入れられている。 前置きが長くなったが、後編となる今回は、消防車以外で電動技術を取り入れた車両・用具を紹介したい。 三輪のEVスクーターを改造した小型ポンプ車両……トーハツ トーハツは、コンパクトな三輪EVの消防バイク「颯」(はやて)を展示。ベースは、EVモーターズ・ジャパンの「BARCA(バルサ)」で、艤装前のスペックで最高速度55km/h。バッテリー容量は5.12kWhで、航続距離は100kmとなっている。 荷台は架装されトーハツの「VE25AS」ポンプを搭載し、2ストローク・ガソリンエンジンで駆動する。 そのほか、バッテリー駆動の電動可搬消防ポンプ「MODEL-1」も展示されていた。 救急に必要な電源をすぐに届ける電源デリバリーバイク……アイディア Aidea(アイディア)は、三輪のEVスクーター「AAカーゴ」の特別仕様車を展示。車載のバッテリーから100Vの電源を出力できるもので、災害時など緊急で電源が必要な場所に迅速に移動でき、ライフラインの確保に役立つ。 EVの「トゥクトゥク」も立派な小型ポンプ車に……サポートマーケティングサービス サポートマーケティングサービスは、消防ポンプを搭載したEVトゥクトゥク「エネバイ」を展示。「シバウラ」製のポンプを荷台に装備している。車体がコンパクトなため、狭い場所へも迅速な展開が期待できる。最大積載量200kg以下で航続距離は90km程度を確保しているという。 電装アシスト「リヤカー」で人力を強力に手助け……ヤマハ発動機 ヤマハ発動機は、次世代型電動ホースカー「X QUICKER(クロスクイッカー)」を展示。基本は人力であるが、高出力なモーター2基が走行をアシストし、坂道などでも楽に引っ張ることができる。約20kmの連続走行が可能だ。