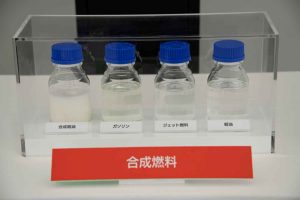日本に何が起こった? BEVが売れない……ハズが2025年10月は電気自動車が売れまくっていた
デイリーEVヘッドライン[2022.11.22]
・東京都、ZEV-Tokyo Festival開催……フォーミュラEがデモラン 【THE 視点】東京をフォーミュラEが走った! 19日(土)に東京都庁前で開催された「ZEV-Tokyo Fes […]