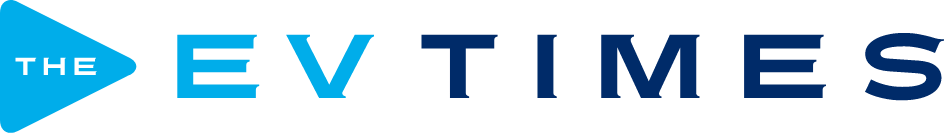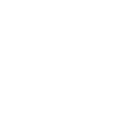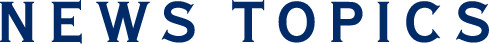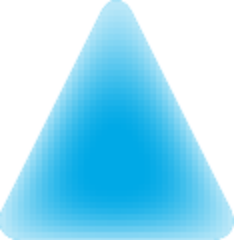バッテリー使用の適正温度とは
寒い冬を迎えると、バッテリーの容量が足りないと実感することがあるかもしれない。電気自動車(EV)で駆動用に車載されるリチウムイオン・バッテリーも同様だ。
バッテリーの出力や充電の性能は、電流と内部抵抗の掛け算によって算出される。内部抵抗とはいわば損失で、温度が下がると電解液の性状やリチウムイオンの移動が低下する特性がある。このため、寒い時期には充電しにくくなったり、あるいは温かな季節にはもっと走行距離を延ばせていた充電残量でも、どんどん電力が減って早めに充電しなければならなくなったりする。
エンジン車でも、たとえば軽油を使うディーゼル車は、寒冷地仕様の燃料でないと冬場に始動できなくなる場合があり、特性を知ったうえで利用することが望まれる。
リチウムイオン・バッテリーに話を戻せば、逆に高温になり過ぎても、熱暴走などといわれる異常な発熱や発火の恐れがある。そこで車載バッテリーを冷却したり、出力を抑えることで温度上昇を防いだりする必要がある。高速道路を走ったあと、急速充電をしようとしてもなかなか充電できないといった事例があるが、これは熱暴走を起こさせないための制御が働くためだ。
一般的に、バッテリーは人が快適に暮らせる温度が適しているともいわれ、昨今のEVは冷却や暖房機能を備えることで、適正温度の範囲で使えるような対策が施されている。ことに液体冷却を採用すると、温度を管理しやすくなる。
三元系リチウムイオン・バッテリーの特徴
初代の日産リーフは空冷によって冷やしながら、正極にマンガン酸リチウムを採用することで熱暴走を防ぐ対策が行われていた。空冷であることによって、廃車後のリチウムイオン・バッテリー再利用のための分解作業がしやすい利点もあった。液体冷却のような強制冷却でなくても、車載バッテリー容量が多くなかったので、走行風を利用することで適性に冷却できた。そのうえ、正極のマンガン酸リチウムはスピネル構造と呼ばれる金属結晶構造を持ち、万一の過充電になっても結晶構造が崩れにくく、短絡(ショート)しにくいので、熱暴走が起きにくかった。リーフが発売されてから、深刻なバッテリー事故が一件も起きていない背景に、こうした慎重なバッテリー採用が機能していた。
一方、スピネル構造は結晶が崩れにくい反面、リチウムイオンを蓄える容量が少なくなる。このため、現在のリーフを含め多くのEVが三元系と呼ばれ、マンガンのほかにコバルトとニッケルという3つの元素をあわせた正極とすることで、容量を増やし、より長い走行距離を実現できるようになった。
層状構造と呼ばれ、リチウムイオンを含む量の多いコバルトは、万一リチウムイオンが抜けきってしまうと結晶構造が崩れてしまいかねない。そこで、リチウムイオンが正極から抜けきってしまうことを防ぐため、充放電の制御をクルマが行うことも重要だ。
EVは充放電の状況を常に監視し、これを製造した自動車メーカーが通信を利用して一台ずつ把握している。したがってEV販売台数の多い自動車メーカーほど、市場でリチウムイオン・バッテリーがどのように充放電されているかの知見を豊富に持つことができる。その実績を基に、どこまで電力を使ってよいのか? 充電ではどこまで負極にリチウムイオンを移動させてよいかを、危険が生じないぎりぎりまで攻め込んだ制御プログラムをつくることができるようになる。いくら机上で計算しても、消費者が市場でどのように使っているかを知らなければ、最大の性能は引き出せない。