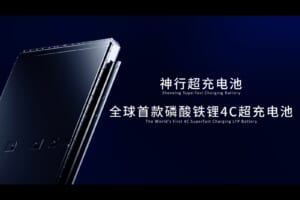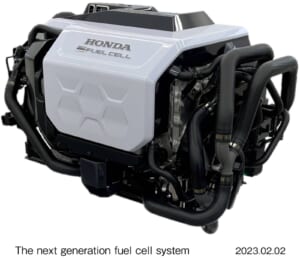ホンダが中国で販売しているBEV(バッテリー電気自動車)の「e:NP1」。前回は外装にフォーカスをあてた。今回はインテリアに注目する。 「ヴェゼル」のボディに「ホンダe」の使い勝手を組み込む エクステリアがまさに「BEV版ヴェゼル」ならば、インテリアもその通りの印象を感じる。エアコンの吹き出し口から分かる通り、根幹をなすダッシュボード付近はヴェゼルと同一だ。 だが、車内を覗き込んで真っ先に目につく15.1インチのタテ型ディスプレイは「e:NP1/e:NS1」にしかない装備である。このディスプレイでナビ、インフォテインメント、エアコン、そして各種アプリケーションの操作を行うわけだ。 また、タテ型の特徴を活かして異なる機能を上下に同時並行で映し出せるため、例えばナビを表示しながらエアコン操作メニューを表示できるなど、実用性にあふれる設計となっているのも特徴だ。 大きめのディスプレイを採用する車種は大抵その反応速度に難があり、日頃使っているスマートフォンのようにサクサク動かない場合がほとんどだが、e:NP1/e:NS1のディスプレイはまったくストレスなく操作が可能であることも評価したい。ホンダeでも同様の印象で、インフォテインメント面におけるホンダの設計の優秀さを感じた。 また、セレクターがホンダeのようなボタン式になっているのもヴェゼルと異なる点である。ホンダのボタン式セレクターは押し心地が大変よく、またレスポンスも良いので個人的には高評価な要素だ。メーターもフル液晶となっており、まさにヴェゼルのボディにホンダeの使い勝手を押し込んだような車という印象を受けた。 室内空間はヴェゼルと変わらない印象だが、これも前回の記事で紹介したようにバッテリーの配置が関係していると思われる。フロア下に張り出す配置でキャビンを圧迫しないようにしているのだろう。 後部座席の足元は本来BEVでは不要なセンタートンネルの盛り上がりが少し確認できるが、気になるほどの高さではない。むしろ、ヴェゼルの時点でその盛り上がりはかなり抑えられており、比較してみてもその高さは両者間で同じのように見える。 これ以外にも内装パーツは多くがヴェゼルとの共通部品であるため、多少なりともコストカットに寄与していることだろう。
#ホンダ