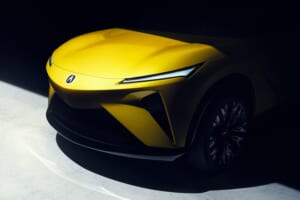多くの非自動車メーカーがEV市場に参入 「ソニー」や「シャープ」など、電気/電子系やIT系のメーカーが近年、EV市場への参入を正式に発表している。こうした話は、コンセプトモデルや将来構想というレベルでは、随分前から国際展示会・見本市、または各社の自社で開催するイベントなどで紹介されることがあった。 そしていま、各社は量産に向けた準備に入ったわけだが、そこにユーザーとしてどんなメリットがあるのだろうか? まず触れておきたいのは、なぜ非自動車メーカーのEV参入が目立つようになったのか、という点だ。そこには自動車産業を取り巻く技術的な環境の変化がある。 2010年代半ば、ドイツのメルセデス・ベンツ(当時ダイムラー)がCASEを提唱した。通信によるコネクテッド、自動(自律)運転、シェアリングエコノミーを活用した新サービス、そしてEVに代表される電動化のことを指す。 それが2010年代後半になると、ESG投資の嵐がグローバルで吹き荒れた。従来のように財務状態だけではなく、環境、ソーシャル(社会性)、ガバナンスを重視した投資のことである。 このトレンドによって、一時期はやや停滞気味だった自動車メーカー各社のEV投資が活発化し、また非自動車メーカーでもESG投資を念頭としたEV戦略を描くようになったといえる。
2025年6月