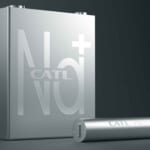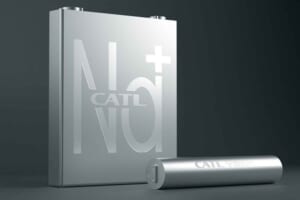Contents
日本のメーカーもEVモデルの開発を加速
テスラのサイバートラックの場合、同社がほかのモデルを販売しているので、充電設備やアップデートのハードルはそれほど高くないと考えられるが、その規格外の大きなサイズや形状など、日本の保安基準に合致していないことが輸入を困難にしている。
保証やアフターサービスの問題も大きい。ICE車の場合、並行輸入業者が独自に保証を提供する場合もあるが、EVでは限定的だ。かつメーカー純正部品の調達や専門的な修理に対応できるかどうかも不透明である。とくに、バッテリーの交換や修理には高度な技術と設備が必要であり、並行輸入業者がこれらに対応できるケースは限られている。
<日本のEV市場の課題と展望>
日本のEV市場は、世界的に見ても普及が遅れている。経済産業省の統計によると、2023年の日本の新車販売に占めるEVの割合はわずか2.0%程度に留まっている。これは、充電インフラの整備不足や、日本メーカーのEVラインアップの少なさなどが要因として挙げられる。
しかし、状況は徐々に変化しつつある。政府は2035年までに新車販売の100%を電動車(EV、PHEV、HEV、FCEV)にする目標を掲げており、充電インフラの整備や購入補助金の拡充などの施策を進めている。また、日本の自動車メーカーも、EVの開発と投入を加速させている。
海外の魅力的なEVを日本で見かける機会が少ないのは残念だが、並行輸入のハードルが高い以上、正規輸入の拡大に期待を寄せるしかない。既存のICE海外メーカーも魅力的なEVを発売しはじめているが、BYDやテスラのように、独自の販売網を構築して日本市場に参入する海外メーカーが増えれば、消費者の選択肢も広がるだろう。
他方、日本の自動車メーカーにとっては、海外の先進的なEVに対抗できる魅力的な製品を開発し、グローバル市場で競争力を高めることが急務となっている。日本のEV市場が活性化し、世界中の優れたEVが日本の道路を走る日が来ることを期待したい。
このようにEVの並行輸入がガソリン車ほど普及しない背景には、単にコストの問題だけではなく、充電規格という物理的制約、法規制による技術的障壁、そしてサポートネットワークの欠如という三位一体の課題が立ちはだかっている。自動車産業が国ごとの規格戦略を推し進める限り、個人が自由に「世界のEV」を選ぶことは容易ではない。この現実は、EV時代の新たな課題として認識されるべきだろう。