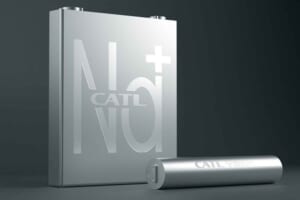ドライバーへの警告音にもなっている
この性質をうまく利用した例として、電車で採用されたインバーターがある。京浜急行の2100形/新1000形(2021年7月で現役引退)で使われた通称「ドレミファ・インバーター」がそれだ。ご存じの方も少なくないだろう。
現在、鉄道の給電方式は直流と交流の2方式だが、古くからある鉄道会社や路線では、その大半が直流を使っている。京浜急行も直流架電だが、効率に優れた交流モーターを使おうと意図した結果、インバーター搭載による交流モーター方式を選択。その際、ドイツ・シーメンス社製のインバーターを採用したのだが、この設計者が遊び心を発揮したらしく、発生ノイズを「ドレミ〜」の音階で刻んだようなのである。厳密にいうと音程は固定ドの「ファソラシ〜」となり、正確にいえばト短調なのだが、きれいに刻まれた音階を一般的な音楽的表現(ハ長調を前提)として「ドレミファ・インバーター」と呼んだものである。
この音階の大もととなったのが、スイッチング素子として使われたGTO(ゲート・ターン・オフ)サイリスタだ。人間が聞く生活環境での中軸可聴帯域となる400Hz付近上下(ハ長調の基準ドは約260Hz、1オクターブ上は520Hz、1オクターブ下は130Hz)の周波数となるため、ドレミの音階付けが容易にできた、というものだ。
ちなみに、スイッチング素子の進化は目覚ましく、GTOサイリスタに代わってより高速なスイッチング動作を行うIGTB(インシュレーテッド・ゲート・バイポーラ・トランジスタ)が登場。EVのインバーターは、このIGBTあたりから主力となり(鉄道は新幹線700系あたりから)、スイッチング周波数が高周波化したことでノイズの発生を抑えることができるようになり静粛化。現在はその次世代となるSiC(シリコン・カーバイド)が使われ始めている。
EVの発生騒音は、基本的には内燃機関車と同じだが、パワーユニットが異なることで、燃焼音、排気音、エンジンメカニカルノイズに代わり、EV固有のインバーター、モーターの周囲からの発生音が新たな問題として浮上してきた。EV独特の「ヒューン」という音もそのひとつだが、車速に応じて騒音レベル(といっても内燃機関車よりはるかに静かだが)が上昇するのは、ドライバーに対する適度な警告音にもなる、という考え方もあるようだ。その気になれば、相当なレベルの静粛性を確保できるEVは、静かなだけにドライバーが走行速度を実感しにくいという性質があり、走行速度に応じた意図的な音作りも必要だろう、という考え方で現代のEVは作られている。
ガソリン/軽油による内燃機関からモーター/電池によるEVへの移行は、単にパワーユニットが変わるのではなく、それを利用して車体を動かす自動車のイメージそのものを変えてしまうことにもなりそうだ。いまの現役世代は、内燃機関車とEVの双方を知ることになるが、将来的にEVしか接することのない世代にとって「過去の」内燃機関車はどのように捉えられるのだろうか、少々気になるところではある。