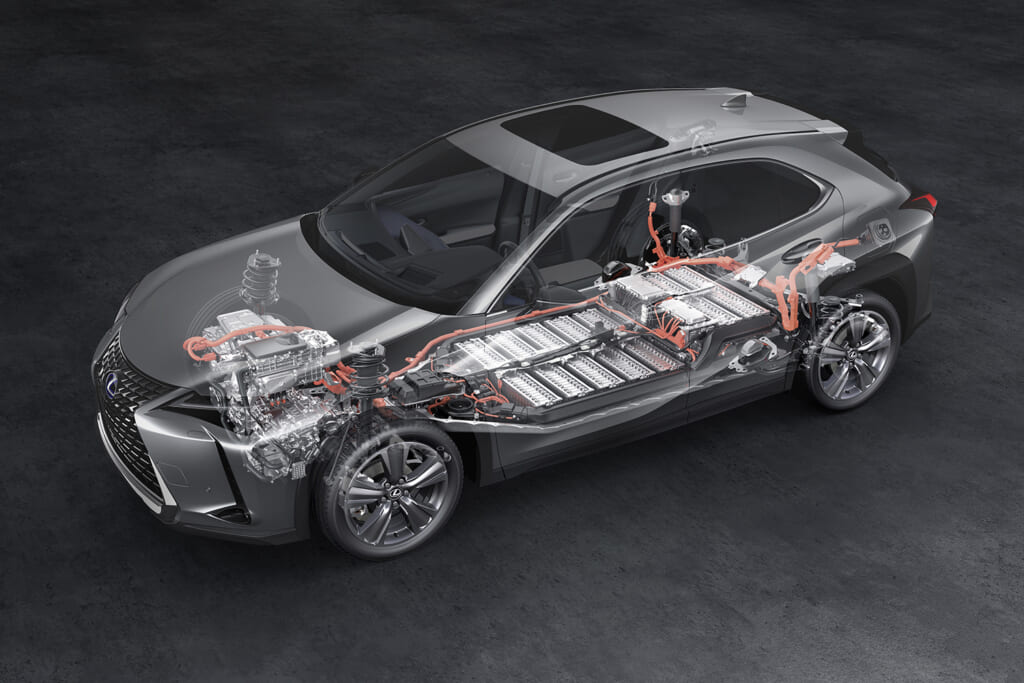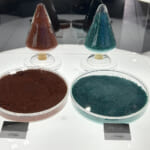今後「スイッチトリラクタンスモーター」が活躍する可能性も
その意味でも注目したいのが、「誘導モーター(IM:Induction Motor)」だ。そもそも同期モーターという呼び名は、交流の周波数と同期して回転するという特性に由来するものだが、逆に交流周波数と回転が同期しないのが、誘導モーターである。
こちらはローターが鉄芯となっていて、ステーターに交流電流を流すことで誘導電流を発生させ、モーターをまわしている。誘導電流につられてローターが回転するのでタイムラグが発生するのが特徴。そのため、非同期モーターと呼ばれることもある。
誘導モーターは磁石を使わないため非常にシンプルな構造で、コスト及び耐久性の面で有利な傾向にある。また、同期モーターに対して高回転(高出力)に優位性をもっている。
ただし、航続距離を確保するという点において、永久磁石を使った同期モーターには2次銅損とよばれるロスが発生しないという特徴がある。そのため、現時点ではPMモーターが航続距離を稼ぐにはベターな選択といえる状況になっている。
だからといって、「未来永劫、EVにはPMモーターを選ぶのが正解!」とはいえないのが難しく、興味深いところだ。
前述したように、永久磁石にはさまざまな調達リスクがある。将来的には永久磁石を使わないことがサスティナブルなEVの条件となる可能性もある。
そうした未来を考えると注目したいのが、「スイッチトリラクタンスモーター(SRM:Switched Reluctance Motor)」だ。鉄芯(ローター)を複数のコイルで構成されるステーターで囲んだ構造で、ステーターに流れる電力を切り換える(スイッチング)ことで、ローターをまわすというのが基本的なメカニズムとなっている。
古くからある形式のモーターだが、上記の構造から振動が大きいというデメリットをもつため、EVの採用例はほとんどない。一方で低コストなのはメリットだ。将来的なEVの低価格化においてはSRMの実用化がポイントになるという見方もある。
いまはモーター駆動のEVには「スムースで振動がない」というイメージが強いが、もしかするとSRMの普及によって振動を味わうような個性的なEVが誕生するのかもしれない。