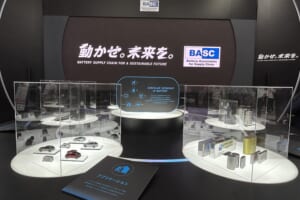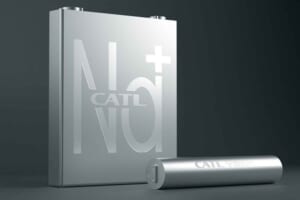ただ再利用すれば解決するほど単純ではない
だが素材リサイクルの前に、EVで使われるリチウムイオンバッテリーの二次利用をもっと進める必要がある。
EVで十分な性能が得られなくなっても、なお70%前後の容量をリチウムイオンバッテリーは残しており、それを単に原料へ戻すリサイクルをしたのでは、生産した際の性能を使い切らずに捨てることになりかねない。したがって、EV後は、まず定置型など含め、容量が0になるまで使い切る二次利用の道を探り、充実させることが先だ。

EVで使い終えたら次の材料へのリサイクルという発想は、20世紀型の着想である。また、リチウムイオンバッテリーとEVとの関係を十分に理解していない、机上の論理に陥りかねない。そこが、分析者たちが陥りやすい落とし穴である。
世界的に、二次利用を着実に事業化しているのは日本の日産自動車だ。
海外でも、EVから外したバッテリーパックをそのまま急速充電に活用する事例がなくはないが、まだ一部にとどまるうえ、何百セルも詰まったバッテリーパックをそのまま転用したのでは、各セル容量を0まで使い切ることはできない。理由は、バッテリーパック内のセルはひとつごとに容量が異なり、それをまとめて使ったのでは、もっとも容量の少ないセルの性能に制約されてしまうからだ。

日産がフォー・アール・エナジー社を通じて実施しているように、少なくともモジュール単位まで分解して利用しなければ、十分な二次利用をしたことにならない。それには、リチウムイオンバッテリーとEVを知り尽くした知見が不可欠だ。
日産以外の自動車メーカーも、あるいは経済の分析者たちも、リチウムイオンバッテリーの本質についてあまりに知識が不足している。それでいながら、持論を展開する危うさがある。
EVとして役割を終えたあとにリサイクルが成り立つかという論議の前に、二次利用によってリチウムイオンを使いつくし、そのうえで材料リサイクルをして採算が合うかどうか。そうした道筋で思考しなければ、意味のない議論で終わってしまう懸念がある。