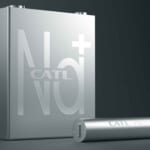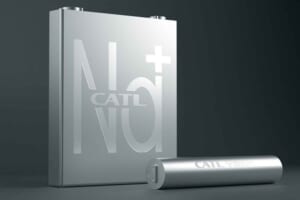軽自動車は海外で販売できない
日本で電気自動車と軽自動車の親和性が高いのに車種の数が限られる理由は、軽自動車が日本独自の規格になるからだ。海外で販売できないと、大量生産によるコストの低減も図りにくい。
ちなみにガソリンエンジンを搭載する一般的な軽自動車も、薄利多売の商品だから、各メーカーとも苦労している。ホンダN-BOXは国内販売の1位で、スズキ・スペーシアやダイハツ・タントも国内販売ランキングの上位に入るが、軽自動車はこのように大量に売らないと採算が成り立たない。電気自動車は、大量に販売できる確証がないため、車種の数も少ない状態が続いている。
しかし、今後は軽自動車規格の電気自動車が増える可能性がある。サクラが成功したからだ。ホンダはN-VAN e:のパワーユニットをN-ONEに搭載したN-ONE e:を2025年中に発売する。
また、ダイハツ/スズキ/トヨタが共同開発した軽商用車規格の電気自動車も、2026年3月までに発売することが発表された。前述のとおり電気自動車は薄利多売だから、複数のメーカーが共同で開発/販売することによってコストを抑える。
軽商用の電気自動車をダイハツ/スズキ/トヨタが共同開発すれば、スバルやマツダを含めて合計5社が扱う可能性も高い。残りはN-VAN e:のホンダと、ミニキャブEV&クリッパーEVの三菱&日産だ。
最近は軽自動車の開発手法も、電気自動車を視野に入れている。たとえばサクラとeKクロスEVのプラットフォームは、ガソリンエンジンを搭載するデイズやeKクロス&eKワゴンと基本部分は共通だ。電気自動車とガソリンエンジン車の両方で、融通を利かせながら活用できる軽自動車のプラットフォームが開発されている。
そのために、今後はN-ONE e:のようなガソリンエンジン車と共通性の多い電気自動車が登場してくる。逆にいえば、ガソリンエンジン車との共通性が得られないと、日本における軽自動車を中心にした電気自動車の本格普及は始まらない。