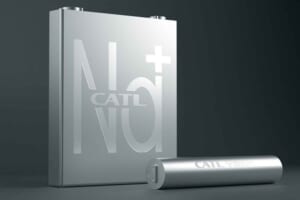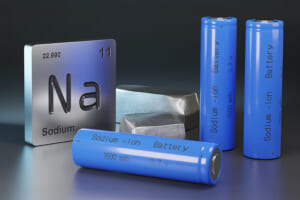リチウム依存からの脱却が現実味を帯びてきた EV用の充放電可能な2次電池は、現在は世界的にリチウムイオン電池が主流を占めているが、ほかに充放電可能なバッテリーはないのだろうか? というのも、リチウムイオン電池の難点は、なんといってもその原材料にレアメタル(希少金属)を必要とすることにある。もちろん、リチウムもレアメタルだが、それよりも希少な存在となっているのがコバルトだ。 このコバルトの埋蔵量で、世界の約半分を占めているのがコンゴ共和国だ。さらに生産量から見るとその比率は70%近くとなり、需要に対してほぼ一極集中と呼べる状態が形作られている。当然ながら、こうした偏った供給体制は、将来的な資源の安定供給という視点から眺めると、きわめて不安定な状態である。じつは、中国がEV化の促進にあたって積極的な体制をとれるのは、その裏付けとして、膨大な資本の投下によるコンゴでのコバルト精錬権の半分以上を手にしているからだ。 こうした現状に留意すると、リチウムイオン電池以外の2次電池にはほかの選択肢はないのかと考えてしまう。そもそも、リチウムイオン電池が着目された理由は、リチウムイオンがもつエネルギー密度の高さにあったためで、この点でリチウムイオンには劣るものの、リチウムイオンとほぼ同時期に考えられた2次電池があった。 それがナトリウムイオン電池である。正極にナトリウム酸化物、負極に炭素系素材、電解液に有機溶媒を使い、ナトリウムイオンが正極と負極の間を行き交うことで充放電が行われる2次電池だ。この点は、リチウムイオンが正極と負極の間を行き交うことで充放電が行われるリチウムイオン電池とまったく同じである。 ナトリウムイオン電池は、リチウムイオン電池とほぼ同じタイミングで研究開発は行われたが、性能的にリチウムイオンにおよばないという判断から、一時開発が見送られた電池である。しかし近年、リチウムイオン電池の資源不足が懸念されはじめるとふたたび着目され、研究開発が本格的に再開されることになった。
#新技術