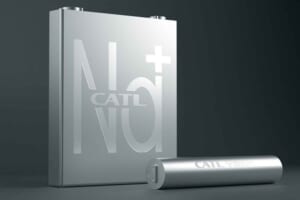TEXT:高橋 優
ファーウェイ&シャオミのEVは価格も性能も戦略も強烈!! スマホ系電気自動車メーカーの勢いがヤバい!
シャオミEVが中国メーカー勢の中心に躍り出た 中国で開催された北京モーターショーにおいて、さまざまな新型EV、および最新EVテクノロジーが発表されました。とくに中国メーカー勢のなかでも、シャオミがその人気の中心となりながら、さらにファーウェイについても、新たなEVブランドであるSTELATOの立ち上げを発表し、ハイエンドセダンS9を発表するなど、中国スマホメーカーという第三勢力の最新動向についてを解説します。 今回取り上げていきたいのが、中国国内で4月末から5月上旬にかけて開催された北京モーターショーです。この中国最大のオートショーについては、上海と北京において隔年で開催されており、昨年の上海モーターショーについては「上海ショック」と題して、多くの日本メディアが、その中国製EVの完成度の高さを報じていました。 そして、今回とくに取り上げていきたいのが、2024年の中国EV市場で台風の目となっているスマホメーカー勢という第三勢力の存在です。まず初めに取り上げていきたいのが、シャオミの存在です。 すでにシャオミについては、4月初頭から初の量産EVであるSU7の納車をスタートしており、順調に生産体制を拡張中です。そして、正式発売がスタートしてから28日が経過した段階で、詳細な注文動向であったり、初のOTAアップデートのタイムライン内容や2024年シーズンにおける納車台数目標、および自動運転のアップデートに至るまでの最新動向が公表されました。 まず初めに、4月24日時点における5000元(約10.8万円)の予約金の返金が不可となる、いわゆるロックインオーダー数が7万5723台に到達している状況です。とくに直近の4日間で5000台以上のロックインオーダーが追加されており、初期注文だけではなく、継続的に確定注文台数が増加していることが示唆されています。 そして、シャオミに対する大きな懸念点でもあったその納車体制について、正式発売をスタートしてから28日間の間に5781台を納車することに成功。とくにEVの量産に関しては、テスラがモデル3において生産地獄に直面し、倒産寸前にまで追い込まれていたという背景が存在したことで、大量の需要を獲得したとしても、それを満足に捌けないのではないかといわれていました。しかし、蓋を開けてみると、納車をスタートしてからものの20日間程度の間に6000台近い車両を納車することに成功したわけです。 その上、当初予定していた生産スピードを引き上げて、6月度においては1万台の納車台数を達成すると主張。2024年シーズンについては、合計10万台の納車台数を実現するという目標も設定してきました。 さらに、すでに納車されたユーザーの内訳について、女性の割合がすでに28%を実現しており、今後その女性率は40%から50%に到達するとも予測されています。その女性率の高さについて理由を調べてみると、エクステリアデザインのよさ、日焼け対策、そして収納の多さという理由が占められています。まさにSU7の強みを、女性ユーザーが高く評価していることが見て取れるわけです。 さらに、ドイツ御三家BBAのオーナーが29%を占めているという点も極めて注目に値します。つまり、ドイツブランドからSU7に流れている様子が見てとれ、これはアメリカでモデル3の爆発的人気とともに、3シリーズやA4、Cクラスの販売台数が低下した流れとまったく同様に感じます。 さらに、アップルユーザーが51.9%と過半数を占めており、やはりこれはCarPlayにも対応しているHyper OSという独自OSを採用しているシャオミの懐の深さが功を奏しているわけです。これによって、SU7を購入したアップルユーザーが、次のスマホの買い替えの際に、シャオミ製のスマホに乗り換えたり、シャオミ製家電を購入する動機づけにもなることから、シャオミのビジネス全体にも好影響を与えるポテンシャルを秘めているわけです。 そして、販売ネットワークについても、2024年末までに46都市、219店舗をカバーする予定です。また、サービスネットワークに関しても、2024年末までに82都市、139店舗をカバー予定。より多くのユーザーにSU7を触れてもらえるような販売ネットワークの拡充とともに、SU7を購入したあとのアフターサービスに関しても、急ピッチで拡充しようとしています。 さらにOTAアップデートについて、ついに初めてのOTAアップデートを5月初旬に配布予定であり、ここではワイヤレスカープレイであったり、エンドトゥーエンドのバレーパーキング、およびそれ以外のスマートな運転体験を配布予定です。 それに続いて、2回目のOTAアップデートについても5月末に実施予定であり、その際にはいよいよ高速道路だけではなく、市街地における自動運転「市街地NOA」をリリース予定です。まずは主要10都市において解放、その後2024年末にかけて、順次、中国全土でのリリースを予定しています。 その上、SU7については、浙江省のトラックレースにおいて1分42秒163という好タイムを記録しています。これはポルシェ・タイカンターボS、およびテスラ・モデルSプラッドを上まわるタイムです。これより上となると、アウディRS e-tron GT、ロータスEletre R+、Zeekr 001 FR、そしてトップのロータスEmeya R+くらいしか存在しないという、EVのなかでもトップクラスのタイムを記録しています。 さらにその上、このラップタイムはあくまでもピレリP ZERO 5という、SU7 Maxに装着される純正タイヤであり、さらに高性能なレーシングタイヤであるミシュランパイロットスポーツCUP2 Rを装着すると、そのタイムは1分38秒043にまで短縮。何といっても、SU7 Maxは29.99万元と明らかに安いわけであり、パフォーマンス性能に対するコスト競争力が抜群に高いことが見て取れます。 そして最後に、この北京オートショーにおける発表会で、シャオミオートへの参画を改めて募集したところ、なんと48時間以内に5000件以上ものレジュメが送られてきているそうです。 いずれにしてもシャオミについては、今後15年以上をかけて世界の自動車メーカートップ5の一角を構成するという野心的な目標を掲げており、採用を強化して、SU7以降のEV開発に繋げていこうとしているわけです。
TAG:
#シャオミ
#ファーウェイ
#中国
#北京モーターショー