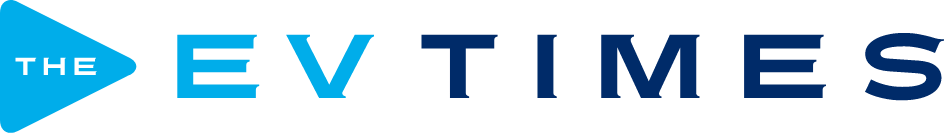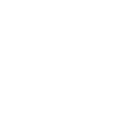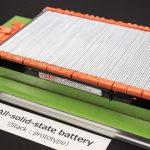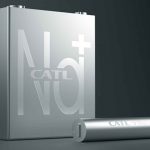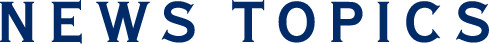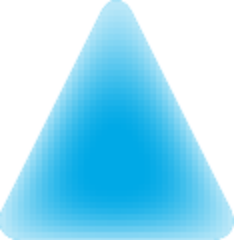EVになると車両重量が重くなる理由
駆動用バッテリーがEVの価格を高くしているほか、車両重量が重い理由もこのバッテリーにあると言われている。
バッテリーは、なぜ重いのか。
ひと言で答えるのはなかなか難しいが、たとえば、補器用バッテリーとして知られる鉛酸バッテリーの電極に使われる鉛は、元素の周期表で82番目であり、26番目の元素である鉄と比べ3.7倍以上重い(周期表上で数字が小さいほうが質量が軽い)。
鉄も鉛も鉱石といって、自然界でつくられた鉱物のうち、人間に役立つ物質だ。
電気自動車(EV)などで使われるリチウムイオンバッテリーの電極に使われる材料で、コバルト、ニッケル、マンガンなどはいずれも鉱石で、周期表ではコバルトが27番目、ニッケルが28番目、マンガンは25番目の元素だ。
三元系と呼ばれる主力のリチウムイオンバッテリーは、この3つの元素を配分して電極をつくっているので、当然それなりの重さになる。
ちなみに鉄は26番目で、アルミニウムは13番目の元素なので、一般に、アルミニウムが軽いといわれるのはそのためだ。鉄は重金属といわれ、鉄以上の重さの金属を重金属としている。アルミニウムは軽金属と区分けされる。
では、コバルトやニッケルより元素番号が小さく、軽いはずの鉄を使ったリン酸鉄のリチウムイオンバッテリーがなぜ重いのかといえば、電極の結晶構造の違いによる。
コバルトやニッケルは、金属としての結晶構造の間に、サンドイッチのようにリチウムイオンを含むため、より多くのリチウムイオンをもつことができる。
一方のリン酸鉄は、電極の結晶構造の隙間に、柱のように結晶を支える構造があり、そこはリチウムイオンが入り込めないので、電極内にもてるリチウムイオンの量が少なくなる。それは、一充電走行距離が短くなることを意味している。
しかしそれでは商品性で、三元系に劣る。そこで、車載量を増やして容量を確保しているため、結果的に重くなる。
EVの特性上バッテリーにガソリンと同じエネルギー量は不要
3元系のバッテリーも、マンガンを含むことで、鉄の結晶と同様に結晶を支える支柱の構造をもつ。多くのリチウムイオンをもてるコバルトやニッケルと、リチウムイオンのもてる量は減っても、結晶構造が崩れにくいマンガンを混ぜることで、3元系の電極は高性能かつ安全の確保も考えられているといえるだろう。
ちなみに、周期表でもっとも軽いのは水素だ。つまり元素番号は1である。また炭素は、6番目の元素だ。つまり、水素と炭素の化合物であるガソリンは、軽い元素を組み合わせた化合物である。
ただし、いくつもの炭素と水素を複合的に組み合わせた化学式をもつので、周期表で軽い元素だから、ガソリンも軽いとはいえない面がある。それでも、容積と重さの関係(比重)でいえば、水より軽いのがガソリンだ。水を1とした場合のガソリンの比重が、0.7程度であることからもわかる。
別の視点として、エネルギー密度を調べると、ガソリンが重量当たり12000whであるのに対し、リチウムイオンバッテリーは200whでしかない。ガソリンの1.6%ほどになる。
つまり、ガソリンと同じエネルギーをリチウムイオンバッテリーで手に入れるには、600倍の重量でなければならない計算になる。
とはいえ、エンジンに比べモーターはエネルギーの変換効率が高い。数値でいえば、エンジンの30~40%に対し90%以上であるため、ガソリンのエネルギーと同じ容量を車載しなくても、走行距離を伸ばすことができる。また、クルマの燃費(EVなら電費)は、停車から発進する際にもっとも悪化する。
エンジンは低回転トルクが小さいのに対し、モーターは低回転のトルクが最大値に達する。つまり、わずかなエネルギーで発進し、速度に乗せていくことができる。
クルマを走らせるという実用において、モーターはわずかなエネルギー消費で日常の用途に十分な加速や速さを得られるため、この点においても、ガソリンと同等のエネルギー量は必要ないといえる。
EVの登場でクルマを提供できるのは自動車メーカーだけではなくなった
ここ数年で一気にEVが普及してから、自動車メーカー以外の参戦も目立ってきた。EVは参入コストが低いことから、新たな市場開拓を狙うのは、企業としては当然の姿勢なのかもしれない。
中国のEV市場の業界図式がいま、目まぐるしく変化している。そのなかでも、家電やスマートフォンのメーカーでもあるHauwai(ファーウェイ)とXiaomi(シャオミ)の存在感が目立つ。
時計の針を少し戻せば、中国ブランドの乗用EVが立ち上がったのは2010年代に入ってからだ。当時、中国各地で中国ブランドEVを試乗したが、クルマの根本的な走行性能のレベルはけっして高くなかった。いわゆるコンバージョンEVという感じであり、EV専用車がAセグメント、またはそれより小さい日本でいう超小型モビリティのような存在が主流だった。電池メーカーもさまざまなブランドが参入し、中国当局は一時、電池の規格化を一気に進めようとしたことを思い出す。
その後、中国政府によるNEV(新エネルギー車)製造に対する支援施策などにより、従来型の外資メーカーと中国地場メーカーの合弁事業のみならず、中国地場ベンチャーが数多く登場することになる。だが、厳しい価格競争や、一部メーカーでの強引な経営体制などの影響で経営破綻したり、ブランドが消滅したりするケースが目立つようになった。
そうしたなか、満を持して登場したのが家電やスマートフォンの製造販売を本業とするHauweiやXiaomiである。背景にあるのは、やはりSDV(ソフトウェア・デファインド・ビークル)という自動車産業における新しい概念だ。
SDVには定義はない。その上で、自動車産業界にとっては2010年代にCASEと呼ばれた次世代技術のなかで、SDVをきっかけに欧米や中国の電機・IT系事業者が自動車産業におけるゲームチェンジを一気に仕掛けてきた形だ。時期としては、コロナ禍であったこともあり、日本の自動車産業界にとってHauweiやXiaomiの自動車産業界における躍進は、寝耳に水といった印象をもっている人が少なくないだろう。
たとえば、Hauweiは自社EVブランド「問界(AITO)」がある。足がかりとして、中国地場では中堅自動車メーカーのセレスと連携して中国での売れ筋である高級SUV EV市場に打って出た。さらに、2023年にはHauweiが中心となる連合体「HIMA」を発足させる一方で、2024年にはセレスがHauweiからAITOの商標権を買収した。
見方を変えると、Hauweiとしては市場における激しい価格競争のなかで完成車事業の収益性を検討し、車載OSなどSDV関連プラットフォームの提供企業として、サレスやHIMAに加入している中国地場大手の上海汽車などと新たな事業展開を目指すものと推測される。
Hauweiの強みとは、EVという商品そのものだけではなく、市場環境や社会情勢によって大胆な経営判断を実行できる経営体制にあるといえるだろう。
桃田健史