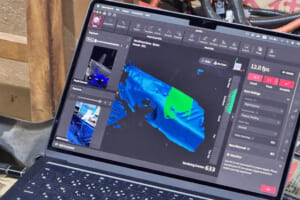中国市場におけるホンダの新型EV試乗記、これまでは内外装のデザインを見てきた。いよいよ走り出してみよう。「e:NP1」はどんな走りを披露してくれるだろうか。 快適性重視のマイルドな乗り味 肝心の乗り心地だが、これも非常に上々な印象だ。もちろん元の「ヴェゼル」ですでに完成度は高いので、あとはそこからどうBEV(バッテリー電気自動車)らしく味付けをおこなうかに焦点を置いたに違いない。 アクセルペダルとブレーキペダルの踏み心地は、昨今のホンダ車らしくスコスコ踏める感覚で、これがとても気持ち良い。全高はそれなりにある車だが、実際に運転してみても不安定感はなく、堅実な足回りの設計を感じた。この点に関してはヴェゼルより少しばかり向上している印象を受けた。 運転中に触るであろうハンドルのボタン類やエアコンの操作、ドライブモードの選択などももたつく反応はなく、運転への妨げは感じられない。ここが「先進性」をうたう車において肝心な部分で、せっかく数々の先進装備を搭載していたとしても、運転中にそれらの操作がストレスなくおこなえなければ本末転倒だと私は思うのだ。 やみくもに画面を増やし、ボタン類をすべてタッチ操作にするよりも、まずは基本的な操作において使用者にストレスを感じさせないことが「日常使いの道具としてのクルマ」で大事な点だろう。 加速感は申し分なく、アクセルを踏めば踏んだ分だけマイルドに加速してくれる。突然「ズドン」と来るような不快感はない。このあたりの制御を日本車はとても得意としているのだ。 BEVをさらに普及させたいのであれば、ガソリン車のドライブフィーリングとの違いを限りなく打ち消す必要がある。この観点から考えても、「e:NP1/e:NS1」が持つ違和感のない乗り心地はとても優秀だと感じた。 「運転しやすい」という表現を「面白くない」と解釈する人もいるかもしないが、決してそういうわけではない。 ちょっとスポーティーな雰囲気を味わいたければ、ドライブモードを「SPORT」に入れることで「NORMAL」よりも締まった走りを提供してくれる。元の車体設計の優秀さが功を奏しているのか、カーブを曲がる際も踏ん張りの効いたコーナリングを感じることができる。 「スポーツBEV」とまでは行かないものの、普通の街乗りに飽きたのなら、通常よりも少しスパイスの効いた走りも選べるというわけだ。良い意味で落ち着いており、気楽に運転できるBEVであるという印象を受けた。
2023年9月